「やる気がなかなか起きない」「モチベーションが上がらず、何をやっても続かない」こんな悩みを抱えている方は多いでしょう。しかし、本記事を読めば、あなたはモチベーションを自在にコントロールする方法を知ることができます。
具体的には次の3つが得られます。
1、今日からすぐに実践できる具体的なモチベーションアップテクニック
2、モチベーションが下がる原因を理解し、根本的に解決する方法
3、継続的にモチベーションを維持する仕組みづくりのノウハウ
この記事は、心理学や行動科学に基づいた信頼性の高い方法を厳選し、実際に多くの人が効果を実感している手法をまとめています。
最後まで読み終える頃には、モチベーションを自分で高め、自然に維持できる状態になり、目標達成や日々の充実感が劇的に変わるでしょう。
モチベーションとは何か?基本知識と定義
モチベーションの正しい意味と仕組み
モチベーションとは、簡単に言うと「やる気」です。
何かをしようとする意欲や行動するためのエネルギーとも言えます。でも、実はただの気分ではありません。目標や望みがあって、それを達成したいという強い気持ちがあるとき、モチベーションは自然に高まるのです。
モチベーションが働く仕組みは次のようになっています。
・「やる理由」が明確になる(例:褒められたい、進学したい)。
・すると、脳の中で「やろう!」という信号が生まれる。
・その信号が行動に移され、実際に勉強などの行動につながる。
つまり、「目標」と「やる理由」が明確なほど、モチベーションは強くなります。
逆に、なぜやるのかがぼんやりしていると、「やる気が出ない…」という状態になりやすくなります。
内発的モチベーションと外発的モチベーションの違い
モチベーションには「内発的」と「外発的」の2種類があります。
内発的モチベーションとは、自分自身の興味や楽しさから生まれるモチベーションです。例えば、好きなゲームをしているときや趣味に打ち込んでいるときに感じる「楽しいからもっとやりたい!」という気持ちがそうです。
外発的モチベーションは、外からのご褒美や報酬などで生まれるモチベーションです。例えば、「勉強を頑張ればお小遣いをもらえる」「仕事を頑張ったらボーナスが出る」といったものですね。
この2つのモチベーションにはそれぞれ特徴があります。
| 種類 | 特徴 | 例 |
| 内発的モチベーション | 長続きしやすい、 楽しさややりがいを感じやすい |
趣味、 好きなスポーツや習い事 |
| 外発的モチベーション | 短期的な目標に有効だが、 報酬がなくなると下がりやすい |
試験のご褒美、 仕事の成果報酬 |
実は、内発的モチベーションのほうが長続きしやすいことが研究でも証明されているのです。アメリカ心理学会(APA)の研究によると、自分自身が楽しさや興味を感じる活動は長期的な行動維持につながりやすいことが分かっています。
逆に、ご褒美がなくなるとモチベーションが落ちやすい外発的モチベーションだけに頼ってしまうと、持続性に欠けてしまいます。
モチベーションが高まるメリットと必要性
モチベーションが高まると、日常生活のいろんな場面で良いことが起こります。
具体的なメリットを以下にまとめました。
・集中力が上がる(短時間でたくさんのことができる)
・成果が出やすくなる(目標達成率がぐんと上がる)
・自信がつく(成功体験を重ねて自信が深まる)
・ストレスが減る(やりたいことがスムーズに進むのでイライラが減る)
例えば、テスト前にモチベーションが高いと、効率的に勉強できます。
結果として良い点数が取れ、自信がつき、次のテストにも前向きに取り組める、という良い循環が生まれます。
大人でも同じことが言えます。職場でモチベーションが高い人は仕事がスムーズに進みます。ストレスが少なくなるので毎日が充実し、さらに大きな仕事にも挑戦できるようになります。
世界的な企業グーグルも、社員のモチベーションを高めることで、生産性やクリエイティブさが増すことを実証しているのです。
モチベーションは自分自身だけでなく、周りにも良い影響を与える重要な要素なのです。だからこそ、モチベーションの仕組みを理解して、自分で高めることが大切なのです。
ここまで読んでくれたあなたも、モチベーションの意味や種類、メリットを知ることで、「なんだかやる気が湧いてきた!」という気持ちになっているかもしれません。
モチベーションの基本を押さえたら、次は具体的にどうやって高めるかを学んでいきましょう。
モチベーションが高まるための必須条件
明確な目標設定とその意義を知る
モチベーションを高めるために一番大切なのは「目標」をはっきりとさせることです。
「なんとなく頑張ろう!」では、やる気はなかなか持続しません。ゴールがはっきりしていると、人は「ここまで頑張ればいいんだ!」と安心し、前向きに行動できます。
アメリカのハーバード大学の研究によると、明確な目標を書き出した人は、そうしなかった人に比べて達成率が大幅に高くなったそうです。なぜかというと、目標を書くことで自分が何をするべきかはっきり分かるからです。
例えば、「テストで80点以上取る!」という具体的な目標があるとします。すると自然に、「そのためには、毎日1時間勉強しよう」という具体的な行動が見えてきます。
「とにかく良い点を取るぞ!」とぼんやりした目標だけだと、何をすればいいか迷ってしまい、結局やる気が続かなくなるのです。
ポイントとして、目標はできるだけ次のように設定しましょう。
・達成可能なレベルにする(難しすぎず、簡単すぎない)
・小さく分けて細かく設定する(達成感を多く味わえる)
目標が明確になると、「達成した!」という成功体験をたくさん味わえます。これが自信となり、次の目標に向けてモチベーションがさらに高まる仕組みができるのです。
挑戦と達成のバランスを適切に保つ
モチベーションをキープするには、「ちょっと難しいけれど頑張ればできる」という、適度なチャレンジが必要です。
あまり簡単すぎると飽きてしまいますし、難しすぎると挫折してしまいます。
このことを心理学の世界では「フロー状態」と言います。
フロー状態になると、時間があっという間に過ぎ、楽しくて集中して作業が進みます。スポーツやゲームに熱中しているときに似ていますね。
例えば、運動が苦手な子どもがいきなりマラソンに出場するとどうでしょう?
多分、途中で嫌になってしまうでしょう。でも、最初は短距離から始めて、徐々に距離を伸ばしていけば、自信がついて楽しめるようになります。
つまり、挑戦と達成のバランスがうまく取れていると、自分の成長を感じられてやる気が出てくるのです。
人間関係や環境整備の重要性
人間は一人だけで頑張り続けるのが難しい生き物です。そのため、周りの環境や人間関係もモチベーションを高めるためにとても大切になります。
学校でも職場でも、「一緒に頑張ろう!」と言ってくれる仲間がいると、自然にモチベーションは上がります。反対に、「どうせ無理だよ」なんてネガティブな人に囲まれていると、やる気がどんどん下がってしまいますよね。
例えば、中学校の部活動でも、一緒に練習を頑張れる友達がいると、「あいつも頑張っているから自分も!」と前向きな気持ちになれますよね。
同じ目標を持つ仲間や、応援してくれる人がいる環境を作ることが大切です。
人間関係以外にも、次のような環境を整えるとやる気が高まります。
・作業机を整理整頓しておく
・やる気が出るアイテム(好きな文房具など)をそばに置く
環境を整えるだけで自然とやる気が出てくるので、ぜひ試してみてくださいね。
心身の健康管理とその影響力
モチベーションを維持するためには、体と心が元気であることが大切です。
「気合いでなんとかなる!」と思う人もいるかもしれませんが、無理をしても良い結果は生まれません。体が疲れていたり、心がストレスでいっぱいだと、どうしてもやる気が続かなくなるのです。
実際、厚生労働省の調査でも、十分な睡眠を取っている人ほどストレスを感じにくく、日中の活動が活発であることが分かっています。十分に睡眠をとり、栄養のある食事を食べることで脳も元気になり、やる気が自然に出てきます。
具体的には次のような健康管理を心がけましょう。
・食事のバランスを意識し、野菜や果物をしっかり摂る
・適度な運動をする(散歩や軽いストレッチでも効果があります)
・疲れたら無理をせず、休憩を取る
例えば、テスト前に徹夜で勉強すると、次の日は頭が働かず逆効果です。むしろ、十分に寝てスッキリした頭で勉強したほうが効率が良いですよね。
体調管理は「やる気」を支える土台です。ここがしっかりしていれば、毎日の生活が楽しくなり、自然とモチベーションも高まっていくでしょう。
モチベーションを上げるための具体的テクニックとコツ
目標を小さく分割して成功体験を増やす
やる気を出して目標を達成したいなら、小さなステップに分けて取り組むことです。
一気に大きな目標を達成しようとすると、「できない」と感じてやる気が下がる場合があります。でも、小さな目標を少しずつ達成していけば、「できた!」という喜びが増えてモチベーションが自然と上がります。
例えば、テスト勉強なら次のように分割してみましょう。
・明日は数学の問題を5問解く。
これを続ければ、毎日達成感を感じて、さらに頑張ろうと思えるようになります。
自分への報酬(ご褒美)制度を設ける
やる気をアップさせるには、自分自身にご褒美を与えるのが効果的です。
人間は何かご褒美が待っていると頑張れる生き物だからです。
例えば、宿題が終わったらゲームを30分できる、勉強を頑張った週末には好きなスイーツを食べる、といった方法です。
こうすることで、「頑張れば楽しいことが待っている」と感じ、モチベーションが上がりやすくなります。
実際に、このやり方は多くの大人も使っています。有名なアスリートや経営者も「自分へのご褒美」を設定して、継続して頑張れる仕組みを作っています。
ポジティブな自己暗示(セルフトーク・アファメーション)を活用する
「ポジティブな自己暗示」とは、自分自身に良い言葉を繰り返すことで自信をつけ、やる気を引き出す方法です。これをアファメーションと呼びます。
例えば、朝起きたら「今日はいい日になるぞ!」や「きっとできる!」と心の中で繰り返してみましょう。最初は少し恥ずかしいかもしれませんが、実際に気持ちが前向きになり、行動に移す力が湧いてくるでしょう。
音楽や動画など気分を切り替えるアイテムを使う
モチベーションが下がってしまったときは、自分の好きな音楽や動画を見ることで気分を切り替えましょう。音楽は脳に働きかけて気持ちを元気にする効果があります。
例えば、スポーツ選手が試合前にお気に入りの音楽を聴いて集中力を高めることがありますよね。それと同じように、自分がやる気になれる曲や動画を見つけておくことがおすすめです。
身体を動かすことで脳をリフレッシュする
体を動かすと脳が活性化して、やる気がアップします。
じっと座ってばかりだと疲れて集中力も下がってしまいます。そんな時は、短い時間でもいいのでストレッチや軽い散歩をしてみましょう。
アメリカの研究でも、軽い運動をすると記憶力や集中力が高まり、勉強や仕事の効率が良くなることが分かっています。勉強の合間に10分ほど散歩するだけでも、かなり効果がありますよ。
ポモドーロ・テクニックなど効率的な時間管理をする
「ポモドーロ・テクニック」は、25分集中して作業したら5分休憩するというサイクルを繰り返す方法です。短い時間に集中できるので、やる気が続きます。
タイマーを使って時間を決めるだけなので簡単にできます。試してみると、集中力が持続しやすく、短時間でも成果を出せるようになりますよ。
仲間と目標を共有し、モチベーションを維持する仕組みを作る
仲間と一緒に目標を決めて頑張ることも、やる気を高めるのに効果的です。
友達や家族と一緒に「今日はここまでやろう!」と目標を決めて、互いに報告し合うと、頑張る気持ちが高まります。
例えば、友達とテスト勉強の目標を決めて、LINEなどで進み具合を共有すると、自然と「負けないぞ!」という気持ちになって頑張れます。
ゲーム感覚で取り組める仕組み(ゲーミフィケーション)を取り入れる
勉強や仕事もゲーム感覚で取り組むと、楽しみながらモチベーションが維持できます。
例えば、自分でポイントやレベルを設定して、達成するごとにレベルアップすると決めます。
・1時間勉強したら10ポイント
・ポイントが100貯まったら特別なご褒美
こんなルールを作ると、勉強や仕事も楽しいゲームのように感じてやる気がアップします。
進捗状況を見える化するためのツールを利用する
自分の進み具合を目に見える形で記録すると、やる気が維持できます。
日記やアプリなどを使って、今日できたことを記録していきましょう。
例えば、「勉強アプリ」や「カレンダーアプリ」を利用して、毎日の努力を記録すると、自分がどれだけ頑張ったかを実感できます。それを見ると、「これだけできた!」という達成感が湧き、次の日も頑張ろうという気持ちになります。
以上のテクニックをうまく組み合わせて、自分に合ったやる気アップの方法を見つけてくださいね。
モチベーション管理の注意点とリスク対処法
目標設定が高すぎると挫折につながる(目標設定の現実性)
モチベーションを上げるために目標設定はとても大切ですが、目標が高すぎると逆効果になってしまうこともあります。
「高い目標のほうが燃える!」という人もいますが、実際は無理な目標に挑戦すると、途中で「無理だ…」と諦めやすくなるんです。
文部科学省の調査でも、自分に合わない難しい目標を設定した人ほど、達成できず挫折感を味わいやすいことが分かっています。これでは本末転倒ですよね。
例えば、普段全然運動しない人がいきなり「1週間後にマラソン大会に出る!」と決めたらどうでしょう?最初はやる気満々でも、すぐに無理だと感じて挫折しやすくなりますよね。こうしたケースはよくあるんです。
そこで、目標は次のポイントを意識しましょう。
・大きな目標は細かく分割して達成感を得やすくする。
こうすれば、無理なくモチベーションを維持しながら達成感も味わえますよ。
他人との比較が逆効果になる理由とその対処法
モチベーションが下がる原因のひとつに「他人との比較」があります。
友達や同僚と比べてしまって、「自分はダメだ…」と思ってしまう経験、ありますよね?誰かと自分を比べすぎると、自信がなくなってモチベーションが一気に下がることがあります。
実際、心理学の調査では、他人と比べすぎる人ほど不安やストレスを感じやすくなることが分かっています。
ここで大切なのは、「比べるのは昨日の自分だけ」という考え方です。
昨日の自分より少しでも進歩していれば、それでいいんです。周りと比較して焦るのではなく、自分自身の成長に目を向けましょう。
・自分の成長を記録して、過去の自分と比較するようにする。
この2つを心掛けるだけで、気持ちがずっと楽になりますよ。
モチベーションだけに依存せず、習慣化する必要性
モチベーションが大事とはいえ、やる気だけに頼るのは危険です。なぜなら、モチベーションというのは気分次第で上がったり下がったりするからです。
気分が良いときしか行動できないようでは、長く続けるのは難しいですよね。
そこで、モチベーションが下がったときでも続けられるように「習慣化」することがポイントになります。
毎日決まった時間に勉強や運動をするといったように、日常のルーティンに組み込むと自然に続けられるのです。
例えば、歯磨きをするのにモチベーションは必要ありませんよね?それと同じで、毎日決まった時間に行動する習慣がつくと、モチベーションに頼らなくても自然と動けるようになるんです。
燃え尽き症候群を防ぐための具体策
やる気がありすぎて無理をすると、「燃え尽き症候群」という状態になってしまうことがあります。これは、頑張りすぎて急にやる気がゼロになってしまうことです。
せっかく高かったモチベーションが一気になくなり、何もやる気が起きなくなるんですね。
厚生労働省も燃え尽き症候群のリスクを指摘しています。頑張りすぎて疲れてしまった人が陥りやすいので注意が必要です。
燃え尽き症候群を防ぐためには、次のようなことを意識しましょう。
・自分のペースを守って無理をしない。
・趣味や好きなことをする時間を作る。
頑張るときと休むときのバランスを上手に取ることがコツですよ。
スランプに陥ったときの有効な対処方法
モチベーションが上がらない「スランプ」は誰にでも起こります。どんなに優秀な人でも、時にはやる気が出なくなる時期が来るものです。
そんな時、「自分はダメだ…」と落ち込まないことが大切です。
スランプになったら、一度立ち止まって次のことを試してみてください。
・やり方を少し変えてみる(勉強場所を変える、新しいやり方を試すなど)。
・誰かに相談する(家族や友達、先生など)。
実際、プロのスポーツ選手や有名な作家などもスランプを経験していますが、そんなときに環境を変えたり、周囲に助けを求めたりして乗り越えています。
自分だけで悩まずに、気持ちを切り替えていくことがとても大切です。
モチベーション管理には、こうした注意点や対処法をしっかり押さえておくと、長く続けていくことができますよ。
モチベーションを上げて維持する具体的な5ステップ

ステップ1:現状把握とモチベーション低下の原因分析
モチベーションを上げるための最初のステップは、まず「今の自分」を知ることです。何に対してやる気が出ないのか、その原因をはっきりさせましょう。
文部科学省の調査では、中学生や高校生の多くが「勉強がつまらない」「目標が見つからない」という理由でやる気を失っていることが分かっています。
大人も同じで、「仕事に意味を感じない」「疲れすぎていて集中できない」といったことが原因でやる気をなくしていることが多いです。
例えば、宿題をやりたくない理由が「苦手な教科だから」なのか「スマホの誘惑が多いから」なのかで対処法が全く違います。
まずはノートやメモ帳に書き出して、自分が何に困っているかはっきりさせましょう。これがモチベーション回復のスタートです。
ステップ2:達成したい目標の具体化と計画の設定
やる気が上がらない原因がはっきりしたら、次に自分が達成したいことを具体的に決めます。「具体的に」がポイントですよ。
「英語を頑張る」ではなく、「次のテストで80点以上取る」と決めることで、目標がはっきりします。
そして、その目標に向かって進むために細かな計画を立てましょう。
・毎日15分、英単語を覚える
・毎晩30分間、問題集を解く
こうやって小さな計画を立てると、やるべきことが明確になって迷いがなくなります。計画を立てると、「自分でもできそうだ!」という気持ちが湧いてきますよ。
ステップ3:自分に合うモチベーションアップ法を選び実践する
次は実際にモチベーションを上げるテクニックを試してみましょう。
人それぞれ合う方法が違うので、自分に合った方法を見つけるのが大切です。
例えば、以下の方法を試してみてください。
・ご褒美を用意して、自分を励ます
・仲間と競争したり励まし合ったりする
・勉強や作業をゲーム感覚で楽しむ(ゲーミフィケーション)
・25分集中したら5分休む「ポモドーロ・テクニック」を試す
色々試していくうちに、「これなら続けられそう!」という方法が必ず見つかりますよ。楽しみながらチャレンジしてくださいね。
ステップ4:記録と可視化で進捗管理を徹底する
モチベーションをずっと維持するためには、自分の頑張りを「見える化」することがとても効果的です。記録をつけて、自分の成長を目に見える形で残しましょう。
例えば、カレンダーに勉強した日をチェックしたり、アプリで進捗を記録したりすると、自分がどれだけ頑張ったかが一目で分かります。
こうすることで、「ここまで頑張れたんだ!」という達成感が生まれて、さらにやる気が出てくるんです。
また、記録を見返して自分を褒める習慣をつけると、もっと前向きに頑張れますよ。
ステップ5:定期的な振り返りと目標の調整で継続力を高める
最後に、定期的に振り返りをして、計画や目標を調整する時間を作ります。
人は状況や気分が変わるので、最初に立てた計画がずっと完璧なわけではありません。
例えば、「毎日1時間勉強する」と決めても、実際にやってみたら難しかった…ということもありますよね。そういうときは無理せず、「毎日30分」や「週に3日は1時間」など、無理のない範囲で計画を調整しましょう。
また、計画通りに進んでいるかどうかを定期的にチェックして、「順調だな」とか「ちょっと頑張りすぎて疲れてるな」など、自分自身の状態を確認します。
このように柔軟に目標を調整していくことで、途中で挫折することなく、長く続けられるんです。無理なく、自分のペースでモチベーションを保っていきましょうね。
モチベーションアップに効果的なおすすめ商品・サービス
モチベーションアップに効果的なおすすめ書籍
やる気がなかなか出ないときには、本を読んで新しい刺激を受けることが効果的です。
特に、やる気を高めたり、自分の心を前向きにしたりする本を選ぶのがポイントです。
文化庁の読書調査によると、本を読むことで気持ちが前向きになったり、行動力がアップしたりする人が多いことがわかっています。だからこそ、やる気を出したいときには本が役立つんですね。
おすすめの書籍をいくつか紹介します。
わかりやすく面白いストーリーで、人生を楽しくするヒントが詰まっています。
目標に向かって諦めずに頑張り続けるコツが書かれていて、続ける勇気が湧いてきます。
集中力を高めて短時間で成果を出す方法を具体的に教えてくれます。
気軽に読める本を手に取って、モチベーションアップを図りましょう!
習慣化と目標管理を助ける便利なアプリ・オンラインツール
毎日の習慣づけや目標管理には、アプリやオンラインツールを使うのが効果的です。
スマホを上手に活用すれば、モチベーションを維持しやすくなります。
実際に、アプリを使って習慣化を成功させた人がたくさんいます。
その中から特におすすめのアプリを紹介します。
仲間と一緒に励まし合いながら目標を達成できるアプリで、仲間と一緒なら頑張れるタイプの人にピッタリです。
勉強時間を記録して可視化できるので、自分の成長が目に見えて、やる気アップにつながります。
習慣を簡単に記録できて、「継続できた日数」が視覚的に表示されるので、
モチベーションが自然と高まります。
無料で使えるものも多いので、自分に合ったアプリを試して、毎日のモチベーションアップにつなげましょう。
集中力や作業効率向上に役立つガジェット類
集中力が続かず作業がはかどらない場合は、便利なガジェットを利用して環境を整えるのがおすすめです。集中しやすい環境を作ることで自然とやる気もアップしますよ。
集中力アップにおすすめのガジェットを紹介します。
周囲の雑音をシャットアウトして、勉強や作業に集中できます。
音楽を聴いてリラックスすることも可能です。
集中と休憩をうまくコントロールするタイマーで、勉強や仕事の効率を高めてくれます。
立った状態で作業ができるデスクで、集中力を維持しやすく、気分転換にも効果的です。
集中力を高める環境を整えれば、自然と作業が進んでモチベーションも上がりますよ。
自己啓発やプロのコーチングサービスの活用法
自分一人で頑張っても、なかなかやる気が出ない時がありますよね。そんなときは、プロの力を借りてみるのもおすすめです。
自己啓発セミナーやコーチングサービスは、やる気を高めるための心強い味方になってくれます。
実際、厚生労働省も、コーチングを受けることで自信がつき、やる気や行動力がアップするという調査結果を公表しています。
具体的には以下のようなサービスがあります。
自分のやりたいことを明確にし、目標達成をしっかりサポートしてもらえます。
家にいながらオンラインでセミナーを受けられ、やる気アップのための実践的なテクニックが学べます。
自分の適性や強みを理解できて、仕事や将来について前向きな気持ちになれます。
プロのアドバイスを受けることで、新しい視点が生まれてモチベーションが高まりますよ。ちょっと行き詰まったなと感じたら、気軽にこうしたサービスを試してみてくださいね。
◆おすすめ「7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画」
【Schoo(スクー)】 ![]() 《スポンサーリンク》
《スポンサーリンク》
まとめ
モチベーションを上げるためには、自分のやる気の仕組みを理解し、具体的なテクニックを試してみることが大切です。
ポイントを振り返ると以下の通りになります。
1、目標は小さく分割する
2、自分に報酬を与える
3、環境を整え習慣化する
4、仲間やツールを活用する
5、定期的に振り返り調整する
ぜひ今日から実践し、モチベーションを維持しましょう。
さらに詳しいテクニックについては【関連記事】「目標達成の仕方を徹底解説!
ビジネスパーソン・学生が成功する7つのステップ」をチェックして下さい。

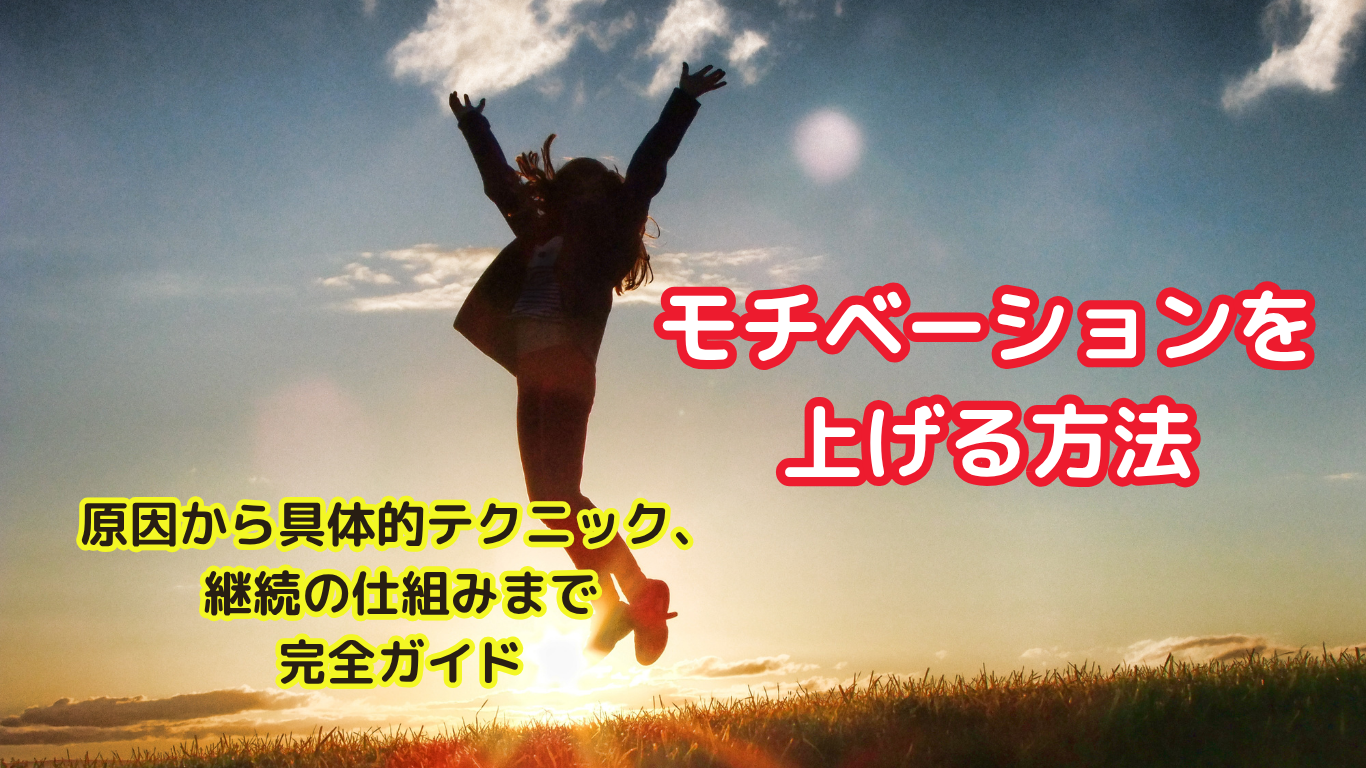



コメント