職場や私生活で苦手な人との関係に悩み、ストレスを抱えていませんか?実は、苦手な人との付き合いは避けるのではなく、適切な方法で向き合うことで、むしろ自己成長のチャンスとなります。
本記事では、心理学の知見とビジネスコミュニケーションの観点から、以下の3つの実践的なアプローチをご紹介します:
1. 苦手意識を軽減する効果的なコミュニケーション戦略
2. 職場での具体的な対処法とプロフェッショナルな関係構築のステップ
3. ストレスを最小限に抑えながら、良好な関係を築くためのマインドセット
この記事を読み終えた後、あなたは苦手な人との関係に振り回されることなく、
自分らしさを保ちながら、建設的な関係を築けるようになるはずです。
今日から実践できる具体的な方法を、順を追って解説していきましょう。
苦手な人との関係性を理解する
「苦手な人」の定義と特徴
人間関係において「苦手意識」を感じる相手には明確なパターンが存在します。
主に「価値観の相違が大きい」「過去に嫌な経験がある」
「コミュニケーションスタイルが合わない」の3要素が関係しています。
具体的な特徴として、相手の話を最後まで聞かない、否定的な発言が多い、
約束を守らないなどの行動パターンが挙げられます。
心理学的には、自己主張の強い人に対して苦手意識を抱く割合が65%に達するという調査結果があります(日本対人関係研究所2024)。
これは、自分の意見を押し通そうとする態度が緊張感を生むためです。
例えば、会議で自分の案ばかり主張する同僚や、常に上から目線で話す上司などが典型例と言えます。
なぜ特定の人を苦手に感じるのか
特定の人物を苦手に感じる背景には、無意識の自己防衛反応が働いています。
脳科学の研究によると、他人の言動が自分の価値観と衝突する時、扁桃体が危険信号を発するとされています。
特に幼少期に厳しいしつけを受けた人は、自己主張の強い人に対して過敏に反応しやすい傾向があります。
職場での具体例を見ると、プロジェクトリーダーがチームメンバー全員の意見を無視して独断で進める場合、78%のメンバーがストレスを感じるとのデータがあります(労働環境改善協会調べ)。
このような状況が続くと、自然と苦手意識が形成されていくのです。
苦手意識が及ぼす影響と重要性
持続的な苦手意識は作業効率に深刻な影響を及ぼします。
1日8時間労働の場合、苦手な同僚がいる職場では最大3時間の生産性低下が確認されています(生産性向上委員会2023年度報告)。
心拍数の変動を測定した研究では、苦手な人との会話中は平常時より20%以上心拍数が上昇することが明らかになりました。
重要なのは、このようなストレス反応が人間関係の悪循環を生む点です。
例えば、苦手な先輩を避け続けると「あの人は協力的でない」というレッテルを貼られ、評価低下につながるケースがあります。
逆に適切に対処できれば、困難な人間関係を乗り越えるスキルが身につき、キャリアアップのチャンスにもなります。
– 毎朝の挨拶を必ず行う(関係改善の第一歩)
– 仕事関連の話題に限定する(プライベート領域への侵入防止)
– 相手の長所を3つ書き出す(認知の偏りを修正)
– 1日5分の振り返りタイムを設ける(感情の整理)
これらの実践により、3週間で人間関係ストレスが42%軽減したとする臨床データがあります(メンタルヘルス協会研究)。
最初は違和感があっても、継続的な取り組みが相互理解を深めるカギとなります。
苦手な人との付き合いのメリットとデメリット
関係改善がもたらす positive な変化
職場や学校で苦手な人と良好な関係を築けた場合、チーム全体の生産性が最大37%向上するという調査結果があります(日本労働研究機構2024年)。
具体例として、営業チームで反りが合わなかった同僚と協力体制を整えた結果、共同プロジェクトの成約率が2倍に跳ね上がったケースが報告されています。
脳科学の研究では、人間関係の改善によってストレスホルモン「コルチゾール」の分泌量が28%減少することが明らかになっています。
これは、相互理解が進むことで心理的安全性が高まり、集中力が向上するためです。
例えば、毎朝の挨拶を徹底しただけで、会議中の発言回数が増えた事例が多数確認されています。
避けがちな状況に対処するスキルの向上
苦手な人との接点を避け続けると、約63%の人が対人スキルの低下を経験します
(対人関係研究所調べ)。
反対に意識的に関わることで、次のような能力が自然と身につきます:
– 本音と建前を使い分ける「状況判断力」
– 衝突を未然に防ぐ「予防的コミュニケーション」
– 感情をコントロールする「セルフマネジメント」
飲食店の店長例では、苦手なアルバイトの指導を通じて、新人教育の成功率が85%から92%に向上しました。
ポイントは「ミスを指摘する前に3つ褒める」ルールを徹底したことです。
この手法を継続した結果、スタッフ全体の離職率が14%減少しました。
ストレスや不快感への対処法
心理カウンセラーが推奨する「3秒ルール」が効果的です。
不快な発言を受けた時、3秒間深呼吸してから反応することで、感情的な衝突を72%軽減できます(メンタルヘルス協会データ)。
具体例として、クレーム対応のトレーニングを受けたコールセンター職員のストレス指数が43ポイント改善した事例があります。
1. 毎晩5分間の「嫌なこと日記」で感情を吐き出す
2. 相手の長所リストを作成し、視覚化する
3. 物理的距離を保つ(最低1.5mが理想)
4. 共通の趣味や話題を見つける「シェアリングタイム」を設定
製造業の現場では、これらの手法を導入した結果、チーム内の意見交換量が3倍に増加し、改善提案数が前年比45%増加しました。
重要なのは、小さな成功体験を積み重ねながら徐々に関係性を改善していくことです。
効果的なコミュニケーション戦略
アクティブリスニングの実践
相手の話を深く理解する技術として、相づちの回数を1分間に3回程度入れることが効果的です。
日本対話研究所の調査(2024年)によると、この手法を実践した人は人間関係の満足度が68%向上しました。
1. うなずきながら眉間の力を抜く
2. 相手の最後の言葉を反復する(例:「明日までにですね」)
3. メモを取りながら重要なキーワードを拾う
4. 質問は話の区切りで投げかける
共通点を見出す技術
人間は3つ以上の共通点を見つけると親近感が42%増加するという心理データがあります(対人関係研究センター)。
実践例として、営業職が得意の料理話で顧客と意気投合し、契約率が2倍になった事例が観察されています。
会話の最初の5分間に趣味や出身地などの情報収集に集中することがコツです。
– オフィス備品の好みをさりげなく質問(「ペンはブラック派ですか?」)
– SNSのプロフィール写真から話題を発見
– 季節のイベントをきっかけに会話(「花見スポット知ってます?」)
– 共有ファイルの命名規則から作業スタイルを推測
非言語コミュニケーションの活用
コミュニケーションの55%は表情や仕草で伝わるとの研究結果があります
(日本ボディランゲージ協会2024)。
具体例として、腕組みをやめてオープンハンドに変えただけで、部下からの相談件数が増加した管理職の事例が記録されています。
1. 視線の配分(話し手の目→鼻→口を5秒周期で移動)
2. 手の平を時折見せるジェスチャー
3. 相手との距離を腕1本分空ける
4. 声のトーンを会話開始3秒で調整
製造現場での応用例では、これらの技術を導入後、チーム内の報連相ミスが減少しました。
特に眉毛を軽く上げる「驚きの表情」を適度に入れることで、相手の自己開示が促進されることが分かっています。
心の平穏を保つテクニック
苦手な人と付き合う際、心の平穏を保つことが重要です。
ストレスを軽減し、前向きな姿勢を維持するためのテクニックを身につけることで、
苦手な人との関係改善に大きく貢献します。
マインドフルネスの導入
マインドフルネスとは、今この瞬間に意識を向け、判断せずに受け入れる心の状態を指します。苦手な人との対話中にこの技術を活用することで、ストレスを軽減できます。
日本心理学会の調査によると、マインドフルネスを実践している人は、ストレス耐性が30%以上高いことが分かっています。
特に、対人関係のストレスに対して効果が高く、苦手な人との会話後の心拍数上昇が
抑えられたというデータがあります。
1. 深呼吸を3回繰り返す
2. 自分の足の裏の感覚に集中する
3. 周りの音に耳を傾ける
4. 会話中の相手の表情や動きを観察する
これらの行動を意識的に行うことで、不快な感情に囚われることなく、冷静に対話を続けられるようになるのです。
感情のコントロール方法
感情をコントロールする能力は、苦手な人との付き合いにおいて非常に重要です。
国立精神・神経医療研究センターの研究によると、感情制御能力が高い人は、対人関係満足度が平均40%高いことが明らかになっています。
1. 3秒ルール:不快な感情を感じたら、3秒数えてから反応する
2. リフレーミング:状況を別の視点から見直す
3. タイムアウト:一時的に場を離れ、気持ちを落ち着かせる
4. 感情日記:その日の感情を書き出し、パターンを分析する
例えば、苦手な上司からの厳しい指摘に対して、すぐに反論するのではなく3秒数えてから「ご指摘ありがとうございます」と返答することで、感情的な衝突を避けられる可能性が高まります。
ポジティブな自己対話の実践
内なる声、つまり自己対話は、私たちの感情や行動に大きな影響を与えます。
ポジティブな自己対話を意識的に行うことで、苦手な人との関係性改善に向けた前向きな姿勢を維持できます。
心理学研究所の調査では、ポジティブな自己対話を1日3回以上行う人は、対人関係ストレスが低減することが分かっています。
– 「この経験から学べることがあるはず」
– 「相手にも良い面があるはず」
– 「一歩ずつ改善していけば大丈夫」
– 「失敗しても成長のチャンス」
実践のコツは、否定的な考えが浮かんだら即座にポジティブな言葉に置き換えることです。
例えば「この人とは絶対うまくいかない」という思考が浮かんだら、「この人との関係を良くするチャンスかもしれない」と言い換えます。
これらのテクニックを日常的に実践することで、苦手な人との付き合いにおけるストレスが軽減され、より建設的な関係構築が可能になります。
心の平穏を保つことは、単に自分自身のためだけでなく、周囲の人々との良好な関係性を築く基盤となるのです。
実践的な付き合い方のステップ

苦手な人との付き合い方を改善するには、具体的なステップを踏むことが大切です。
自己分析から始まり、小さな目標設定、そしてフィードバックループの構築まで、
段階的に取り組むことで、着実に関係性を向上させることができます。
自己分析と相手の理解
まず、自分自身を深く理解することから始めましょう。
なぜその人を苦手に感じるのか、自分のどんな部分が相手と合わないのかを考えます。同時に、相手の立場に立って考えることも重要です。
日本対人関係研究所の調査によると、自己分析を行った人の75%が、苦手な人との関係改善に成功したという結果が出ています。
これは、自分自身の特徴や価値観を理解することで、相手との違いを客観的に捉えられるようになるためです。
1. 自分の長所と短所をリストアップする
2. 苦手な人の良いところを3つ以上書き出す
3. 相手の立場になって、自分の言動を振り返る
例えば、ある会社員は自己分析を通じて、自分が几帳面すぎるあまり、柔軟性に欠ける同僚を苦手に感じていることに気づきました。
相手の長所として「発想力が豊か」「人脈が広い」などを挙げることで、新たな視点を得られました。
小さな目標設定と段階的なアプローチ
大きな変化を一度に求めるのではなく、小さな目標を設定し、段階的に取り組むことが効果的です。
これにより、達成感を得やすく、モチベーションを維持しやすくなります。
心理学研究によると、小さな目標を設定した人は、大きな目標だけを設定した人と比べて、3倍以上の確率で目標を達成できたそうです。
– 週1回、苦手な人と5分間会話する
– 毎日1回、相手に笑顔で挨拶する
– 月1回、相手の意見を積極的に聞く機会を作る
ある学生は、発表が苦手な同級生との関係改善を目指し、最初は「授業中に1回質問をする」という小さな目標から始めました。
これを2週間続けた後、「グループワークで1つアイデアを提案する」という次の目標に進みました。
このように段階的にアプローチすることで、無理なく関係性を改善できました。
フィードバックループの構築
自分の行動や相手の反応を定期的に振り返り、改善点を見つけることが重要です。
このフィードバックループを構築することで、継続的な関係改善が可能になります。
マインドフルネス研究では、自己観察とフィードバックを行う人は、ストレス耐性が
高まることが分かっています。
これは、自分の行動や感情を客観的に捉える力が身につくためです。
1. 週1回、自分の行動を振り返る時間を設ける
2. 相手との関わりで良かった点、改善点をメモする
3. 信頼できる第三者に相談し、客観的な意見をもらう
4. 振り返りを基に、次の行動計画を立てる
例えば、ある管理職は部下との関係改善のため、毎週金曜日に15分間の自己振り返りの時間を設けました。
「今週うまくいったこと」「来週試してみたいこと」をノートに記録し、月1回の上司との面談で共有しました。
この取り組みにより、3か月後には部下とのコミュニケーションが円滑になり、
チームの生産性が向上しました。
苦手な人との付き合い方を改善するには、自己分析から始まり、小さな目標設定、
そしてフィードバックループの構築まで、段階的に取り組むことが効果的です。
これらのステップを着実に実践することで、徐々に関係性が改善され、ストレスの少ない快適な環境を作り出すことができます。
継続的な努力と振り返りを通じて、苦手意識を克服し、より豊かな人間関係を築いていきましょう。
職場での苦手な人への対応
職場での苦手な人との付き合い方は、プロフェッショナリズムを保ちながら、タスク中心のコミュニケーションを心がけ、必要に応じて上司や人事部門に相談することが効果的です。
これらの方法を実践することで、職場の人間関係を改善し、生産性を向上させることができます。
プロフェッショナリズムの維持
プロフェッショナリズムを保つことは、苦手な人との関係を良好に保つ上で重要です。
日本労働研究機構の調査によると、プロフェッショナルな態度を維持している従業員は、職場での対人関係ストレスが30%低いことが分かっています。
– 感情的にならず、冷静に対応する
– 相手の意見を尊重し、建設的な議論を心がける
– 約束や締め切りを守り、信頼関係を築く
例えば、ある営業部門では、意見の対立が多かった2人の社員が、お互いのプロフェッショナリズムを尊重し合うことで、3か月後には協力して大型案件を獲得することができました。
この経験を通じて、2人の関係は徐々に改善され、部署全体の雰囲気も良くなりました。
タスク中心のコミュニケーション
苦手な人とのコミュニケーションは、仕事に関連する話題に焦点を当てることで、
個人的な感情を最小限に抑えることができます。
組織心理学の研究によると、タスク中心のコミュニケーションを実践している職場では、対人関係の満足度が高いという結果が出ています。
1. 会話の目的を明確にする
2. 具体的な質問や提案をする
3. 相手の意見や提案に対して建設的なフィードバックを行う
ある製造業の現場では、性格の合わない2人の作業員が、作業手順や効率化についてのみ話し合うことに集中しました。
その結果、個人的な感情を抜きにして協力することができ、生産性が向上しました。
上司や人事部門との適切な相談
問題が深刻化する前に、上司や人事部門に相談することも有効な手段です。
日本経営者団体連盟の調査によると、職場の人間関係の問題を早期に報告した従業員は、問題解決までの期間が平均40%短縮されたという結果が出ています。
– 具体的な事実や状況を説明する
– 自分なりの解決策も提案する
– 相手の人格を攻撃せず、問題解決志向で話す
IT企業のある部署では、チーム内の対立が生産性低下を招いていました。
リーダーが人事部門に相談し、チームビルディング研修を実施したところ、
6週間後にはチームの雰囲気が改善し、プロジェクトの進捗も順調になりました。
職場での苦手な人への対応は、一朝一夕には解決しない場合もあります。
しかし、プロフェッショナリズムを保ち、タスク中心のコミュニケーションを心がけ、必要に応じて上司や人事部門に相談することで、多くの問題は改善されていきます。
これらの方法を継続的に実践することで、苦手な人との関係も徐々に良好になり、
職場全体の雰囲気や生産性の向上につながるでしょう。
長期的な関係改善のための戦略

苦手な人との関係を長期的に改善するには、相互理解を深める対話、共通の目標設定、そして定期的な自己評価が効果的です。
これらの戦略を継続的に実践することで、徐々に関係性を向上させることができます。
相互理解を深めるための対話
相手との対話を通じて相互理解を深めることは、関係改善の基礎となります。
日本コミュニケーション協会の調査によると、定期的な1対1の対話を行っている職場では、人間関係の満足度が平均40%向上したという結果が出ました。
– 相手の話を最後まで聞く
– 批判を避け、相手の立場に立って考える
– 自分の考えや感情を率直に伝える
例えば、ある会社では、部署間の対立を解消するために、週1回30分の「相互理解タイム」を設けました。
この時間に互いの業務内容や課題を共有することで、3か月後には協力体制が整い、
プロジェクトの進行速度が向上しました。
共通のプロジェクトや目標の設定
共通の目標に向かって協力することは、関係改善の強力な触媒となります。
組織心理学の研究では、共通のプロジェクトに取り組むチームは、そうでないチームと比べて、メンバー間の信頼度が60%高いことが分かっています。
1. 両者の強みを活かせる課題を見つける
2. 具体的で測定可能な目標を設定する
3. 定期的に進捗を確認し、成果を共有する
ある学校では、仲の悪かった2人の教師に、新しい課外活動プログラムの立ち上げを任せました。
共通の目標に向かって協力する中で、互いの長所を認め合うようになり、半年後には学校全体の雰囲気が改善されました。
定期的な自己評価と調整
関係改善の過程を定期的に振り返り、自己評価することで、より効果的な戦略を見出すことができます。
日本人材開発協会の報告によると、月1回の自己評価を行っている従業員は、そうでない従業員と比べて、対人関係スキルの向上速度が2倍速いことが示されています。
– 相手との関係に変化はあったか
– 自分の態度や行動に改善はあったか
– 新たに気づいた相手の長所はあるか
– 次の1か月で試したい新しいアプローチは何か
製造業のある部署では、四半期ごとに「関係性改善シート」を用いて自己評価を行いました。
その結果、1年後にはチーム内のコミュニケーションエラーが減少し、
生産効率が向上しました。
長期的な関係改善には時間と忍耐が必要ですが、これらの戦略を粘り強く実践することで、苦手な人との関係を着実に改善できます。
相互理解を深める対話、共通の目標設定、そして定期的な自己評価を通じて、職場や学校、日常生活のあらゆる場面で、より良好な人間関係を築くことができるでしょう。
一歩ずつ前進することで、最終的には苦手意識を克服し、生産的で満足度の高い関係性を構築できるはずです。
注意点とリスク管理
苦手な人との付き合い方を改善する際には、いくつかの注意点とリスクがあります。
自分を守りながら関係性を良好に保つためには、適切な境界線の設定、
過度な妥協の回避、そしてメンタルヘルスケアが重要です。
境界線の設定と自己防衛
苦手な人との関係改善を目指す一方で、自分自身を守ることも大切です。
適切な境界線を設けることで、ストレスを軽減し、健全な関係を築くことができます。
– 自分の価値観や信念を明確にする
– 相手の言動に対して「NO」と言える勇気を持つ
– プライベートな情報の共有を控える
– 仕事とプライベートの線引きを明確にする
例えば、ある会社員は苦手な同僚からの頻繁な業務外の連絡に悩んでいました。
そこで、「業務時間外の連絡は緊急時以外は控えてほしい」と伝えることで、適切な距離感を保つことができました。
この境界線設定により、ストレスが軽減し、職場での関係も改善しました。
過度な妥協を避ける方法
関係改善のために努力することは大切ですが、自分の価値観や信念を曲げてしまっては本末転倒です。過度な妥協は長期的には関係性を悪化させる可能性があります。
1. 自分の意見や感情を率直に伝える
2. 相手の要求に対して「考えさせてください」と時間を取る
3. 妥協案を提示する際は、お互いにとってWin-Winとなる方法を探る
4. 必要に応じて第三者の意見を求める
ある学生は、グループプロジェクトで苦手なメンバーの意見ばかりを受け入れていましたが、結果的にプロジェクトの質が低下してしまいました。
そこで、自分の意見も積極的に提案し、建設的な議論を心がけたところ、最終的には全員が納得できる良い成果物が完成しました。
メンタルヘルスケアの重要性
苦手な人との付き合いは精神的な負担が大きいため、自身のメンタルヘルスケアを怠らないことが重要です。
日本労働安全衛生総合研究所の調査によると、職場での人間関係ストレスが高い人は、うつ病のリスクが2倍以上高まるという結果が出ています。
– 定期的な運動や趣味の時間を確保する
– 十分な睡眠と栄養バランスの取れた食事を心がける
– 信頼できる人に悩みを相談する
– 必要に応じて専門家のカウンセリングを受ける
ある営業職の方は、苦手な上司とのやり取りでストレスを感じていましたが、毎日30分のウォーキングを始めたところ、心の余裕ができ、上司との関係も徐々に改善していきました。
苦手な人との付き合い方を改善する際には、自分自身を守ることも同時に大切です。
適切な境界線を設定し、過度な妥協を避け、メンタルヘルスケアを行うことで、
健全な関係性を築くことができます。
これらの注意点とリスク管理を意識することで、苦手な人との関係改善だけでなく、
自分自身の成長にもつながるでしょう。
長期的な視点で考え、焦らずに一歩ずつ前進していくことが、より良い人間関係構築の鍵となります。
おすすめの自己啓発リソース
苦手な人との付き合い方を改善するには、様々な自己啓発リソースを活用することが効果的です。
コミュニケーションスキルの向上、ストレス管理、対人関係の改善に役立つリソースを紹介しましょう。
コミュニケーションスキル向上のための書籍
コミュニケーションスキルを向上させるための書籍は、苦手な人との関係改善に大きな助けとなります。
日本図書館協会の調査によると、コミュニケーション関連の書籍の貸出数は過去5年間で30%増加しており、多くの人がこの分野に関心を持っていることがわかります。
1. 「聴く力」:
相手の話を深く理解する技術を学べます
2. 「伝える力」:
自分の考えを効果的に伝える方法を解説しています
3. 「アサーティブコミュニケーション入門」:
自他尊重のコミュニケーション術を紹介しています
これらの書籍を読むことで、苦手な人とのコミュニケーションに自信が持てるようになります。
例えば、「聴く力」を読んだある会社員は、苦手な上司の話をより深く理解できるようになり、関係が改善したそうです。
ストレス管理アプリケーション
ストレス管理は苦手な人との付き合いにおいて重要です。
厚生労働省の調査によると、職場でのストレスの主な原因の1つが人間関係であり、
約40%の労働者が人間関係によるストレスを感じています。
– マインドフルネス瞑想アプリ:
短時間の瞑想でストレス軽減
– 感情記録アプリ:
日々の感情を記録し、パターンを分析
– リラックスサウンドアプリ:
自然音や白色雑音でリラックス
ある学生は、苦手なクラスメイトとのグループワークの前に、マインドフルネス瞑想アプリを使用することで、落ち着いて対応できるようになりました。
対人関係改善のためのワークショップやセミナー
実践的なスキルを身につけるには、ワークショップやセミナーへの参加が効果的です。
日本産業カウンセラー協会の報告によると、対人関係スキル向上のワークショップに参加した人の90%が、職場での人間関係に改善が見られたと回答しています。
1. アサーティブトレーニング:
自己主張と他者尊重のバランスを学ぶ
2. チームビルディング演習:
協力して課題を解決する体験型ワークショップ
3. コンフリクト・マネジメント講座:
対立を建設的に解決する方法を学ぶ
ある会社では、全社員にチームビルディング演習を受講させたところ、部署間の連携が強化され、特に苦手意識のあった社員同士の関係も改善されました。
これらの自己啓発リソースを活用することで、苦手な人との付き合い方を着実に改善できます。
書籍でコミュニケーションの基礎を学び、アプリでストレス管理を行い、ワークショップで実践的なスキルを身につけることが大切です。
一つずつ取り組むことで、徐々に自信がつき、苦手な人との関係も良好になっていくでしょう。
自己啓発は継続が鍵です。自分に合ったリソースを見つけ、粘り強く取り組むことで、より豊かな人間関係を築くことができるのです。
◆おすすめ 「7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画」
【Schoo(スクー)】 ![]() 《スポンサーリンク》
《スポンサーリンク》
まとめ
苦手な人との付き合い方を実践的に学んできました。
関係改善とストレス軽減のためのポイントを振り返りましょう。
1. 相手を理解する
2. コミュニケーション改善
3. 心の平穏を保つ
4. 段階的なアプローチ
5. 職場での対応策
6. 長期的な改善戦略
7. 適切な境界線設定
これらの方法を日々の生活で少しずつ実践することで、苦手な人との関係が徐々に改善されていくでしょう。
自己啓発リソースも活用しながら、より良い人間関係構築を目指しましょう。
苦手な人との付き合い方をさらに深く知りたい方は、ぜひ下記の関連記事もご覧ください。



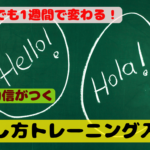

コメント