「自分の強みがわからない…何が得意なのかすら見つからない」
そんなふうに悩んでいませんか?
就職や転職、あるいは自己成長のために「自分の強み」を知りたいと思っても、何から始めればいいのかわからず立ち止まってしまう方は少なくありません。
この記事では、そんな悩みを抱えるあなたに向けて、「無料で受けられるオンライン診断」や「実践的な自己分析のやり方」を中心に、わかりやすく解説していきます。
■本記事で得られる3つのこと
1、無料で使えるおすすめの強み診断ツールがわかる
2、診断結果を深掘りする自己分析の具体的なフレームワークを学べる
3、自分の強みを活かせる仕事や働き方のヒントが見つかる
これらの情報は、筆者自身の実体験や、多くのユーザーの口コミを元にまとめていますので、信頼性も十分。
記事を読み終える頃には、あなた自身の強みが「言語化」され、自信を持って日常や仕事に活かす第一歩を踏み出せるはずです。
自分の強みとは何か?基礎知識とその重要性
『強み』の意味を解説:自分だけの得意な資質とは
「強み」とは、単に得意なことを指すわけではありません。
人それぞれが持っている“自然にできてしまうこと”“努力せずに結果が出ること”の中に、本当の強みが隠れています。
たとえば、話を聞くのが上手な人、アイデアを出すのが得意な人、地道な作業をコツコツと続けられる人など、それぞれの「無意識の才能」が強みにつながります。
実際に、厚生労働省のキャリア形成支援サイトでは、強みの定義を「他者に比べて、繰り返し安定して高い成果を出せる資質や行動」と示しています。
つまり、「ほかの人より自分が少しだけ得意なこと」や「いつも自然と任されること」に目を向けると、強みが見えてくるのです。
以下のような特徴があれば、それは強みの兆しかもしれません。
・苦手意識がないまま高い成果を出せる
・他人に説明すると「それすごいね」と言われる
・自分にとっては当たり前なのに、周囲が驚く
たとえば、整理整頓が得意な主婦が「家の収納を人に教えるようになった」、アイデアマンの営業職が「提案力を評価され昇進した」というケースは典型です。
つまり、「自分が無意識でできるけど、他人には難しいこと」に気づくことが、強みを見つける第一歩になります。
自分の強みを知る重要性:仕事や人生にもたらすメリット
自分の強みを知っている人は、進むべき方向に自信を持ちやすくなります。
逆に、「自分に何ができるか分からない」状態では、目の前のことに振り回され、やりたいことも見えなくなりがちです。
日本の就労者を対象にしたマイナビの調査(2022年)では、「自分の強みが分かっていない」と答えた人が全体の約45%にのぼりました。
つまり、約2人に1人が自分の強みに迷っているということになります。
しかし、強みを明確にしておくと、次のようなメリットがあります。
・就職・転職活動で自己PRがしやすくなる
・自分に合った働き方やライフスタイルを選びやすくなる
・周囲との役割分担やチームワークがしやすくなる
・ストレスが減り、モチベーションが持続しやすい
たとえば、営業が苦手だった人が、自分の「細かい分析力」に気づいたことで、事務や企画職に転向して活躍したという話もよくあります。
自分の強みを理解し、それを活かした環境に身を置くことで、無理なく成果を出せるようになるのです。
これは、人生全体の満足度を上げる大きな要素にもなり得るのです。
「強み」とは、自分らしく輝くためのヒント。
まだ明確でなくても大丈夫です。
この記事を読み進めながら、少しずつ探っていきましょう。
「強み」と言えるための3つの条件
「自分の強みがわからない」と感じている方は多いですが、実は“本当の強み”には共通する特徴があります。
それが次の3つの条件です。この3つを満たしていれば、あなたが今見過ごしていることも立派な強みかもしれません。
① 継続して高い成果が出せること
まずひとつ目の条件は、「何度やっても良い結果が出せること」です。
一度だけ成功したことではなく、日常的に他の人よりも上手くやれてしまうことが該当します。
・プレゼンやスピーチで毎回高評価を得る
・お客様対応でいつも「あなたに話せてよかった」と言われる
・企画提案で採用率が高い
こういった「再現性のある成果」は、あなたが意識していなくても立派な強みの証拠です。
厚生労働省が定義する“コンピテンシー”(職務で成果を出すための行動特性)も、この「一貫して高い成果を出せる資質」であることが前提となっています。
また、強みとは資格やスキルだけに限りません。
たとえば「丁寧に作業を仕上げる」「空気を読むのが得意」なども、十分に価値ある強みです。
② やっていて苦にならず自然体でいられること
ふたつ目の条件は「それをやるのが苦にならない」ということです。
むしろ楽しくて、あっという間に時間が過ぎてしまうようなもの。それは“無意識に発揮できる力”であり、才能に近いものでもあります。
次のような特徴が当てはまるなら、それは強みの可能性大です。
・長時間集中して取り組める
・他人が面倒に感じることでも、楽しんでできる
・自分では特別な努力をしていないつもり
たとえば、書類のミスを見つけるのが得意な人、誰とでもすぐ打ち解けられる人、細かい作業をずっと続けられる人などが該当します。
これらはすべて「苦にならない=自然体で結果が出せる」という観点から強みといえまるでしょう。
心理学者マーティン・セリグマンが提唱した「ポジティブ心理学」でも、自分が楽しく取り組める活動を“シグネチャーストレングス(署名的な強み)”と呼び、幸福度との深い関連性を認めています。
③ 周囲に良い影響を与えていること
三つ目の条件は「周囲の人にプラスの影響を与えているかどうか」です。
他人から感謝されたり、頼られたりする行動は、あなたにとって自然でも、周囲には貴重な強みに見えている可能性があります。
・「○○さんに相談したらスッキリした」と言われた
・困っている人を自然にフォローできて感謝された
・「一緒に仕事すると安心する」とよく言われる
こういったフィードバックは、自分では気づかない強みを教えてくれる大きなヒントになります。
実際、リクナビNEXTの「グッドポイント診断」では、18種類の強みのうち
「親密性」「感受性」「柔軟性」など、他者との関係性の中で発揮されるタイプの強みも多く取り上げられています。
つまり、「自分がやっていることで、誰かの役に立っているか?」という視点は非常に重要です。
家族や同僚、友人からの評価や何気ない一言の中に、あなたの強みが表れていることは珍しくありません。
この3つの条件をすべて満たしていることは少なくても、2つ以上該当すれば“立派な強み”と考えてOKです。
自分では気づかないことが多いので、強み診断ツールや周囲の声をヒントにするのがオススメです。
「得意なこと=強み」ではなく、「成果」「楽さ」「周囲への貢献」の3軸で見つめ直すことが、真の強み発見への近道になります。
強み診断ツールを使ってみた実例と口コミ
体験談:無料診断ツールで見つけた私の強み
「自分の強みが本当にわからない」。そんな思いから、私の知人のKさんは、いくつかの無料強み診断ツールを実際に試してみました。
最初に使ったのは「リクナビNEXT」のグッドポイント診断だったそうです。
会員登録は必要でしたが、18種類の強みの中から自分に合った5つを提示してくれるということで、まずは軽い気持ちで受けてみたそうです。
診断結果では、「親密性」「挑戦心」「現実思考」「冷静沈着」「自己信頼」が自分の強みとされました。
どれも意外性があるようで、じつは普段の仕事や人間関係の中で無意識に発揮していたもの。特に「現実思考」は、問題に直面したときに感情よりも事実や分析を重視する
Kさんの傾向そのものでした。
さらにミイダスの「コンピテンシー診断」も受けてみました。
こちらは、かなりの設問数があり時間も20分以上かかりますが、その分だけ細かく
「行動特性」や「適職」「ストレス耐性」などがわかるのが魅力です。
結果として「人と深く関わる仕事が向いている」と出たとき、Kさんの選んできたキャリアが強みに合っていたのだと安心できたそうです。
このように、診断結果は単なる占いではなく、過去の経験や無意識の行動に気づくヒントになります。
特に就活や転職のタイミングでは、自分の軸が定まっていないと迷走してしまうことも多いので、ツールを活用して自己理解を深めるのは非常に有効だと感じました。
利用者の口コミ:人気強み診断ツールの評判を紹介
Kさんの体験だけでは偏ってしまうため、SNSやレビューサイトなどで実際のユーザーの口コミも調べてみました。
以下に、代表的な無料診断ツール5つについての評判をまとめます。
| 診断ツール名 | よく聞く評価 | 特徴 | 対象者 |
| リクナビNEXT 「グッドポイント診断」 |
無料なのに精度が高い、 就活で使いやすい |
強み5つを提示、解説付き | 就活生・20代の転職希望者 |
| ミイダス 「コンピテンシー診断」 |
適職・市場価値まで 出るのが良い |
ボリュームあり、 詳細な分析 |
キャリアの方向性に 悩む社会人 |
| 16Personalities | 楽しい、 当たってる感じがする |
性格タイプ診断+強み傾向 | 軽く自己理解したい人 |
| マイナビ「適性診断MATCH plus」 | 学生向けっぽいが、 自己理解に役立つ |
性格傾向・向いてる仕事が 分かる |
就活前の学生 |
| OfferBox「AnalyzeU+」 | 精度が高く、 企業側も見るらしい |
大学生向けの詳細診断 | インターン・新卒向け |
※口コミ出典:X(旧Twitter)や口コミ掲示板、就活系ブログなど
ポイントとしては、「どこまで深く分析したいか」で選ぶべき診断が変わってくることです。
軽く自分を知る程度なら16Personalities、本気でキャリアの方向を見直したいならミイダス、エントリーシートに使える強みを知りたいならリクナビNEXTが使いやすいという声が多く見られました。
口コミの多くに共通するのは「思った以上に当たっていた」「自分を見直すきっかけになった」という感想でした。中には「逆に当たりすぎて怖い」という反応もありましたが、それだけ客観的な質問と論理的な設計がなされているという裏返しとも言えるでしょう。
これらの診断を活用することで、ただ「強みがわからない」と悩む状態から、「もしかしたらこうかも?」というヒントを得られるようになります。
自分一人では気づきにくい特性を浮き彫りにしてくれる、まさに“鏡”のような役割を果たしてくれるツールです。
このように、体験者としてのリアルな声や、実際の口コミからも、強み診断ツールが多くの人にとって役立っていることがわかります。
診断を受けるだけでも、自分の中にある小さな自信のタネが芽生える感覚を、ぜひ味わってみてください。
自分の強みを見つけるコツ・診断ツールの選び方
目的別・強み診断ツールの選び方(就活・転職・自己理解)
「どの診断ツールを使えばいいの?」と悩む方は少なくありません。
実は、目的に合わせて使うツールを選ぶことで、得られる気づきや納得感が大きく変わります。診断結果がしっくりこない場合は、自分に合っていないツールを選んでいる可能性もあります。
以下に、目的別の選び方を表にまとめました。
| 目的 | おすすめ診断ツール | 特徴 |
| 自己理解を深めたい | 16Personalities、 グッドポイント診断 |
性格タイプや資質の傾向がわかる |
| 就活・新卒採用対策 | AnalyzeU+、MATCH plus | 企業が見ている資質を可視化できる |
| 転職・キャリア見直し | ミイダス、 グッドポイント診断 |
適職や市場価値まで提示される |
それぞれの診断には向き・不向きがあります。
たとえば、16Personalitiesは自分の傾向をざっくり知るのに向いていますが、転職活動にはやや情報が物足りないかもしれません。
一方、ミイダスの診断は精度が高いものの、設問数が多く疲れるという声もあります。
診断に正解はありませんが、「どんな場面で使いたいか」「自分が知りたいことは何か」を明確にするだけで、ツール選びはぐっと楽になります。
診断結果を自己分析に活かすコツ:SWOT分析で強みを深掘り
ツールの結果をそのまま終わらせてしまっては、もったいないです。
大切なのは、診断で得られた「言葉」や「資質」を、実際の経験と照らし合わせて自分のものとして落とし込むことです。
ここでおすすめなのが、ビジネスでも活用される「SWOT分析」。本来は企業戦略に使われるフレームワークですが、個人にも応用できます。
・Strength(強み):診断で得られた資質やスキル
・Weakness(弱み):苦手なこと、うまくいかなかった経験
・Opportunity(機会):強みを活かせそうな環境・仕事・人脈
・Threat(脅威):成長を妨げる要因、今の環境の課題
実際に紙やノート、PCに書き出して整理すると、自分の強みがどんな状況で発揮されやすいのか、どのように活用すべきかが見えてきます。
たとえば、「協調性」が強みとして出た人がSWOT分析を通じて、「チームで成果を出す環境でより力を発揮できる」と気づき、営業よりもプロジェクトマネジメントの道へ進んだというケースもあります。
周りの人に聞いてみる:第三者の視点で強みを確認
診断ツールも分析も試したけれど、今ひとつピンとこない。
そんな時は、身近な人の力を借りてみるのも一つの方法です。実は、自分のことは自分が一番見えていないというのはよくある話。だからこそ、他人の視点が貴重なのです。
・信頼できる同僚や上司
・家族や親しい友人
・過去に一緒に何かを成し遂げた人
・「私の得意なことって何に見える?」とシンプルに尋ねる
・「いつも○○なとき、私どう見えてた?」と具体的に聞く
・もらった言葉はメモしておく(意外なキーワードが出てくる)
筆者自身、昔の同僚に「あなたの強みは、場の空気を読む力」と言われて驚いた経験があります。自分では“ただ気を使っているだけ”だと思っていた行動が、他人から見ると信頼の源だったことに気づきました。
また、複数人に聞いて共通して出てくるワードは、かなりの確率で“本質的な強み”といえるでしょう。自分一人では見逃してしまう価値を、他人のフィードバックが教えてくれるのです。
診断ツールはあくまで「気づきのきっかけ」です。本当の強みは、それを自分の経験や行動と結びつけてこそ見えてきます。
目的に合ったツール選びと、SWOT分析・周囲からの客観的な視点の活用。
この3つのステップを押さえることで、あなたの「まだ知らない強み」が、きっと輪郭を持ち始めます。
強み診断ツール利用時の注意点とリスク
診断結果は絶対ではない:鵜呑みにせず自分で取捨選択
強み診断ツールは便利な自己理解の手段ですが、出てきた結果をそのまま信じるだけでは不十分です。
あくまで「傾向」を教えてくれるものであって、「真実」ではありません。
例えば、ある診断で「社交性」が強みと出ても、人前で話すのが苦手と感じている人にとっては違和感があります。
これは、診断が過去の回答傾向から導き出した「可能性」であり、必ずしもあなたの実感と一致しないこともあるからです。
また、厚生労働省の職業適性調査でも「性格診断だけで職業を決めるのは望ましくない」と明記されています。環境・経験・育った文化など、性格以外の要素もあなたの強みに影響するためです。
・診断結果は「ヒント」として受け止める
・経験や実績と照らし合わせて、納得できる部分を取り入れる
・違和感がある部分はスルーしてOK
ツールを使うときの心構えとして、「自分で選び、自分で意味づける」姿勢がとても大切です。
迷ったら複数の診断を活用:結果を比較して精度アップ
ひとつの診断結果だけで判断すると、内容に偏りが出ることがあります。
そんな時は、複数の診断を受けて比較してみるのが効果的です。
異なる設問やロジックで導かれた結果を見比べることで、自分の強みに一貫性があるか、逆にばらついているかが見えてきます。
たとえば、以下のように使い分けるとより立体的に自分を理解できます。
| 診断ツール | 特徴 | 向いている目的 |
| リクナビNEXT グッドポイント診断 |
資質ベースの強み分析 | 就活・転職用の自己PR作成 |
| ミイダス コンピテンシー診断 |
適職・ストレス傾向まで可視化 | キャリア見直し |
| 16Personalities | 性格傾向をタイプ別に提示 | 自己理解・人間関係の把握 |
共通して出てきたワードや傾向は、あなたの中にある“核”の部分である可能性が高いです。
逆に、診断ごとに結果がバラバラな場合は、答え方やそのときの心理状態によって影響を受けている可能性もあります。
・2〜3種類のツールを受ける
・結果を一覧にして書き出す
・重なるキーワードに注目する
・違っている点にも意味がないか検討する
比較しながら自分の特性を“言語化”していくことで、診断結果を「使える情報」に変えることができます。
強みがない人はいない:焦らず自分のペースで見つけよう
診断を受けても「ピンとこなかった」「自分には強みがない」と感じて落ち込む人もいます。でも安心してください。強みが「ない」のではなく、「見つかっていない」だけです。
たとえば、農林水産省の「職業能力評価基準」では、「日常的に行っている作業や行動も職業能力として十分評価される」と記載されています。
つまり、特別な才能やスキルでなくても、続けてきたこと・人から感謝されたことには価値があるのです。
・人と比べて優れていなくても「自分らしさ」が強みになる
・強みは後から育つこともある
・変化の中で新しい強みに気づくこともある
例えば、学生時代に地味に続けてきた部活のマネジメント経験や、家族との関係で身につけた気配りも、立派な資質です。
誰かと比べず、過去の自分と向き合うことが、強みを発見する一番の近道です。
強み診断ツールはとても便利ですが、「使い方次第」で得られるものは大きく変わります。
・複数のツールを比較して傾向を見る。
・そして「強みがない」と思い込まず、小さな特徴に目を向けていく。
この3つを意識することで、強み探しの旅はきっと、もっと楽しくなります。
焦らず、あなたのペースで進めていきましょう。
就活・転職にも役立つ自分の強み発見6ステップ

STEP1:オンラインの無料強み診断を受けてみる
まず最初のステップは、自分の強みに対する“客観的なヒント”を得ることです。
そこで役立つのが、無料で受けられるオンラインの強み診断ツールです。
たとえば、リクナビNEXTの「グッドポイント診断」では、18種類の強みの中から自分に合う5つを抽出してくれます。
また、ミイダスの「コンピテンシー診断」では、職務適性やストレス耐性なども可視化され、より実践的な結果が得られます。
厚生労働省の「職業能力評価基準」も、個人の資質や適性を把握することの重要性を説いています。
自己判断だけでは見落としがちな強みを、テスト形式で明らかにしてくれることがツールの利点です。
STEP2:診断結果を分析し、強みの候補を洗い出す
診断を受けただけで終わりにせず、その内容を「自分の言葉」に置き換えることが大切です。
提示された強みの名称だけを見るのではなく、「なぜその強みがあると判断されたのか」を振り返りましょう。
・診断結果の強みを1つずつノートに書き出す
・「自分は本当にそうなのか?」と問いかけてみる
・過去の経験や行動と一致する点にチェックを入れる
このように、診断と実体験を照らし合わせることで、表面的な言葉ではなく“根拠のある強み”として意識できます。
STEP3:過去の成功体験を振り返り強みを裏付ける
次に行うのは、自分の過去の「うまくいった出来事」を棚卸しすることです。
特別な成果でなくて構いません。例えば、バイトで褒められたことや、家庭内でいつも頼られていたことも立派な材料です。
・なぜそのときうまくいったのか?
・どんな行動が評価されたか?
・自分にとって苦ではなかった点は何か?
たとえば、イベントの企画が成功したなら「計画性」や「調整力」が強みと言えるかもしれません。
このプロセスによって、診断結果に対する「自分なりの確信」が持てるようになります。
STEP4:信頼できる人に自分の強みをフィードバックしてもらう
自分一人では見つけられない強みも、他人の目にははっきり見えていることがあります。
だからこそ、自分をよく知っている人に聞いてみるのが効果的です。
・家族や友人
・職場の上司や同僚
・学生時代の恩師や先輩
・私ってどんなとき頼りにされてる?
・私の長所や強みって何だと思う?
・私の良さが発揮されていた場面はどこ?
複数の人に聞いて、共通して出てきたキーワードは、あなたの本質的な強みである可能性が高いです。
STEP5:見つけた強みを3〜5個に絞って言語化する
情報を集めたら、今度は「使えるかたち」に整える作業が必要です。
就活や転職活動では、自分の強みを端的に伝える力が求められます。
・相手の気持ちを自然とくみ取る共感力
・ゴールまで地道に取り組む継続力
・複数の情報を整理して要点を伝える構成力
また、「○○のような場面で発揮された」という具体例を1つ添えておくと、説得力が一気に増します。
この段階で強みが3〜5個に絞れていると、自己PRや志望動機の軸としても活用しやすくなります。
STEP6:自分の強みを活かせる仕事・業界を探してみる
最後のステップは、見つけた強みを「どう活かすか」を考えることです。
自分の強みを発揮しやすい環境に身を置くことで、無理せず成果を出しやすくなります。
たとえば:
| 強み | 向いている仕事の傾向 |
| 計画性がある | プロジェクト管理、経理、人事 |
| 共感力がある | 福祉、医療、接客業 |
| 分析が得意 | データ分析、マーケティング、研究職 |
経済産業省の「社会人基礎力」でも、仕事選びには「自らの強みと業務内容のマッチ」が非常に重要とされています。
また、転職エージェントやキャリア相談などを活用して、自分の強みを伝えた上で仕事を探すと、ミスマッチを減らすことにもつながります。
この6ステップを順番に進めていけば、自己理解が深まるだけでなく、将来の選択にも自信が持てるようになります。
診断から始まり、自分自身と対話し、人からの声も取り入れながら、
「あなただけの強み」を探してみてください。
おすすめの無料強み診断ツール5選
無料で使える強み診断ツールは数多くありますが、どれを選べばいいのか迷う人も多いはずです。
ここではおすすめの診断ツールを5つご紹介します。
それぞれに特徴や向いている人が異なるため、目的に合わせて使い分けるのがコツです。
リクナビNEXT「グッドポイント診断」(18種の強みから自分の強み5つを診断)
リクナビNEXTが提供する「グッドポイント診断」は、転職活動中の社会人に特に人気があります。
会員登録(無料)が必要ですが、所要時間は約30分ほど。
18種類の強みの中から、あなたに合った5つを診断してくれます。
・診断結果は保存され、履歴として残せる
・自己PRや職務経歴書にもそのまま使える表現が並ぶ
・質問形式がやや多めだが、設問の精度が高い
実際試されたSさんの場合:
「柔軟性」「挑戦心」「親密性」「現実思考」「冷静沈着」という結果に。
Sさんの感想:
『まさに自分の性格や過去の働き方にフィットしており、驚いたと同時に「このままの自分でいいんだ」と思えました。』
ミイダス「コンピテンシー診断」(強み・適職だけでなく市場価値もわかる)
ミイダスの診断は、企業の人材分析でも使われる「コンピテンシー(行動特性)」をベースに設計されています。
強みの診断だけでなく、自分に向いている職種や行動傾向、ストレス耐性、マネジメント適性なども詳細にわかります。
・設問数が多く、時間は20〜25分程度
・グラフで視覚的に傾向を確認できる
・結果に対する解説もかなり具体的
特に「市場価値レポート」は他では得られない内容で、自分の年収期待値や求められている業界が一覧で出てきます。
自己理解にとどまらず、次のキャリア選択に役立てたい人におすすめです。
16Personalities(16タイプの性格診断で適職や強みのヒントを得る)
世界中で使われている定番の無料性格診断。
心理学のMBTI理論に基づいて、自分の性格タイプ(全16種類)をわかりやすく提示してくれます。日本語にも対応しており、回答は10分ほどで完了します。
・あなたの性格タイプと特徴
・対人関係の傾向
・適職や働き方のヒント
例えば「建築家タイプ(INTJ)」と出た場合、「戦略的で計画力があり、独立性が強い」といった解説がついてきます。
診断後に共有しやすいURLも表示されるため、友人同士で比較するのも面白いです。
マイナビ「適性診断MATCH plus」(性格や価値観からあなたに合う職種を診断)
マイナビが提供する学生向けの適性診断ですが、大人が使っても非常に参考になります。質問は30問前後と少なめですが、シンプルに「どの職種が自分に合っているか」が分かりやすく提示されます。
・就職・転職活動で業界選びに迷っている
・性格や価値観とマッチする仕事を探したい
・手軽に診断を受けたい人
診断結果には「あなたに合う5つの職種」や「特徴的な思考傾向」などが載っており、
働くイメージを膨らませやすくなります。
OfferBox「適性診断AnalyzeU+」(約250問で性格・強みを詳細に分析)
就活生に人気のサービスOfferBoxが提供しているこの診断は、設問数は多め(約250問)ですが、その分とても詳細なデータを返してくれます。
・性格の傾向
・社会性、積極性、柔軟性などのスコア化
・問題解決力や行動パターンの特徴
診断後は、自己分析シートのPDFもダウンロードできるため、エントリーシートや面接準備にも直結します。学生向けに設計されていますが、社会人が自己理解を深めたいときにも非常に有用です。
これら5つの診断ツールは、どれも無料で利用でき、それぞれ異なる強みを持っています。
大切なのは「どの情報が自分にとって使いやすいか」を見極めることです。
目的や状況に応じてツールを使い分けながら、自分の強みを多角的に探ってみてください。強みを知ることは、これからのキャリアにも自信を持つ大きな一歩になります。
◆おすすめ「7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画」
《スポンサーリンク》
![]()
まとめ
この記事では、「自分の強みがわからない」と悩む方に向けて、診断ツールの活用法や自己分析のステップを紹介してきました。
自分の資質に気づくことで、就活・転職にも自信が持てるようになります。
焦らず、少しずつ前に進んでいきましょう。
1、無料診断で強みのヒントを得る
2、自己分析で結果を深掘りする
3、強みを活かせる仕事を探す
▶【関連記事】「完全版・自己分析のやり方10選!簡単にできる方法と志望動機への活かし方」はこちらから。




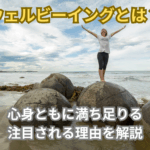
コメント