私たちが何気なく使う「ありがとう」という言葉。
実はこの小さな習慣が、人生の質を大きく左右することをご存じでしょうか。
心理学の研究では、感謝を日常的に意識する人ほど幸福度が高く、ストレスに強く、良好な人間関係を築きやすいことが明らかになっています。
とはいえ「感謝の気持ちを持とう」と頭でわかっていても、日常生活の中で自然に習慣化するのは簡単ではありません。
そこで本記事では「感謝 習慣 効果」というテーマを軸に、感謝がもたらす具体的なメリットと、その効果を実感できる実践法を紹介します。
感謝のリストアップ法やフィードバックの伝え方、睡眠や免疫力への影響まで、科学的根拠と実際の事例を交えながら解説していきます。
今日からでも取り入れられる小さな習慣で、あなたの心と人間関係に大きな変化が訪れるはずです。
なぜ「感謝」が人生を豊かにするのか?
心理学的に証明された「感謝」と幸福度の関係
感謝を習慣にすると、人はより幸せを感じやすくなります。
これは心理学の研究で繰り返し確認されてきた事実です。アメリカ心理学会(APA)の報告によると、感謝を日常的に意識する人は抑うつ症状が少なく、幸福度が高い傾向があるとされています。
なぜ感謝が幸福感につながるのかというと、人は不満や不足に意識を向けやすい生き物だからです。
しかし、日々の小さなことに「ありがたい」と感じる習慣を持つことで、視点が不足から充足へと移り変わります。その結果、心の中に「満たされている」という感覚が積み重なり、幸福度が上がるのです。
例えば、米国カリフォルニア大学デービス校の心理学者ロバート・エモンズ博士の研究では、「感謝日記」をつけたグループはそうでないグループに比べ、日常の満足度が25%以上高まったと報告されています。
このデータは「感謝」が単なる気分の問題ではなく、科学的に幸福感を引き上げる行為であることを示しています。
実際の生活でも、感謝を習慣にした人は小さな変化を体験しています。
例えば、毎晩寝る前に「今日よかったことを3つ」書き出すだけで、気分が安定し、日常の中で良い出来事に目が向くようになります。小学生でも続けられるシンプルな方法ですが、その効果は非常に大きいです。
つまり、感謝を心理的に取り入れることは「不足感を減らし、満足感を増やすスイッチ」と言えます。
この習慣は誰でも今日から始められるシンプルな行動でありながら、人生全体を豊かに変える力を持っているのです。
感謝がもたらす脳内ホルモンの働き
感謝の習慣には、脳の働きを変える効果もあります。
感謝の気持ちを抱くと、脳内で「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンやオキシトシンが分泌されることがわかっています。
これらのホルモンは心の安定や安心感を生み出し、人とのつながりを強める働きを持っています。
国立精神・神経医療研究センターの資料でも、セロトニンはストレスに対する耐性を高め、気分を安定させることが示されています。
さらに、オキシトシンは「愛情ホルモン」とも呼ばれ、信頼や絆を深める働きがあると報告されています。
つまり、感謝は脳の生理的な仕組みを通じて、人をリラックスさせ、安心した気持ちに導いてくれるのです。
具体例を挙げると、ある企業で「感謝を伝えるメール習慣」を導入したところ、社員同士の信頼感が高まり、離職率が減少したというケースがあります。
これは単に人間関係が改善しただけでなく、感謝の言葉が脳に働きかけ、安心感や結束感を引き出した結果だと考えられるのです。
また、家庭でも同じことが起こります。
夫婦で一日の終わりに「今日ありがとうと思ったこと」を言い合うだけで、脳が安心を感じ、関係性が深まります。
小さな習慣が脳内のホルモン分泌を促し、互いの信頼感を自然に強めていくのです。
つまり、感謝は「気分を良くするだけの習慣」ではなく、脳科学的にも幸福を後押しする行動です。セロトニンやオキシトシンといったホルモンの働きが、感謝の効果を裏付けています。
感謝を習慣化することのメリット
ストレス耐性とメンタルヘルスの改善
感謝を日常的に意識することは、ストレスに強い心を育て、精神的な健康を守る大きな助けになります。
なぜなら、感謝の習慣は不安や怒りといったネガティブな感情を和らげ、心のバランスを整える働きがあるからです。
厚生労働省の「こころの健康」資料でも、ストレス対処法のひとつとして「前向きな感情を意識する」ことが紹介されています。
感謝はその最もシンプルで効果的な方法のひとつといえます。
また、米国国立衛生研究所(NIH)の研究では、感謝の習慣を持つ人はそうでない人に比べ、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌量が23%低いという結果も示されています。
例えば、受験勉強や仕事で疲れているときに「自分を支えてくれる家族がいる」「食事を用意してくれる人がいる」と感謝を思い出すことで、不安や緊張が和らぐことがあります。この小さな気づきが、心を安定させるクッションの役割を果たすのです。
さらに、感謝日記をつける実践例では、不安障害を抱えていた人が「毎晩3つのありがとう」を書き続けることで、半年後に不眠が改善し、気分の落ち込みも軽減したという報告があります。
小さな習慣が大きな心の変化をもたらすことを裏付ける好例です。
結局のところ、感謝はストレスをただ減らすだけではなく「心の免疫力」を高める習慣です。
続けるほどに気持ちが安定し、困難に直面しても折れにくい心をつくっていきます。
人間関係をスムーズにする効果
感謝の習慣には、人間関係を円滑にする強力な効果もあります。
人は「認められている」と感じることで心が安心し、相手への信頼感を深めるからです。
総務省の「国民生活に関する世論調査」では、人との信頼関係が厚い人ほど生活満足度が高いと報告されています。
つまり、感謝の言葉を交わし合うことは単に礼儀作法ではなく、互いの幸福度を底上げする仕組みでもあるのです。
具体例を挙げると、ある学校では「ありがとうカード」を導入しました。
生徒がクラスメイトに感謝を伝えるカードを書いて渡す取り組みです。
その結果、いじめの件数が減り、クラスの雰囲気が明るくなったと報告されています。これは、感謝の習慣が信頼と尊重を育み、人間関係を円滑にした明確な実証です。
また、ビジネスの現場でも同じことが起きています。
上司が部下の努力に感謝を言葉で伝える職場は、離職率が下がり、チーム全体の生産性が上がる傾向があります。
小さな「ありがとう」が人を動かすエネルギーになるのです。
結論として、感謝の習慣は人と人を結ぶ「見えない架け橋」といえます。
続けるほどに信頼が積み重なり、対人関係の摩擦が少なくなり、結果的に人生そのものが歩みやすくなるのです。
感謝がもたらすビジネスへの好影響
職場での信頼関係構築に役立つ理由
感謝を表すことは、ビジネスの現場において信頼関係を築く最も効果的な方法のひとつです。
単に「ありがとう」と伝えるだけで、相手は自分の努力が認められたと感じ、安心感やモチベーションが高まります。
厚生労働省が公開している「働き方と職場の人間関係に関する調査」では、職場の人間関係満足度が高い社員ほど仕事への意欲も強く、離職率が低い傾向があると報告されています。
つまり、感謝の文化は人材の定着にも直結する要素です。
さらに、米国の人事調査機関Globoforceのレポートでは、「感謝や称賛を受ける機会が多い従業員は、生産性が31%向上する」と発表されています。
数値から見ても、感謝は職場の成果を押し上げる確かな要因です。
実際の例を挙げると、ある日本企業では「感謝カード」を導入しました。
社員同士が日常業務での助けや努力を互いにカードで伝える仕組みです。その結果、部署間の連携が強まり、プロジェクトの進行が円滑になったと報告されています。
感謝が単なる礼儀にとどまらず、実務効率にも直結する証拠といえます。
結局のところ、感謝を習慣にした職場は「互いに認め合う安心感」が生まれ、信頼が積み重なる環境になります。これはチームの力を最大限に引き出す土台です。
リーダーシップと感謝の関係性
リーダーにとって感謝の姿勢は欠かせません。なぜなら、部下やチームに対して感謝を示すことが、強いリーダーシップを発揮するための重要な要素だからです。
経済産業省の「働き方改革実行計画」関連資料でも、上司からのフィードバックや承認が社員のパフォーマンスを高めると指摘されています。
感謝を伴った言葉が加わることで、部下は「自分は組織に必要とされている」と感じやすくなるのです。
例えば、世界的なIT企業Googleでは「心理的安全性」が高いチームほど成果を上げることがわかっています。
心理的安全性を支える要素のひとつが「リーダーが部下の貢献を感謝する姿勢」です。感謝の有無が、チームの挑戦意欲や発言のしやすさを左右するのです。
日本企業のケースでは、上司が定例会議で「小さな努力」まで感謝を口にしたところ、部下が自ら新しい提案を出すようになったという事例もあります。
感謝は指示や管理では生まれにくい「自発的な行動」を引き出す効果を持っています。
まとめると、感謝はリーダーシップの本質的な力です。
権威や役職に頼らず、人を動かすエネルギーとなるのが感謝の言葉です。結果として組織全体の雰囲気が前向きになり、長期的な成果を生み出す基盤につながります。
感謝の習慣を身につけるステップ
1日3つの「ありがとう」を書き出す
感謝を習慣にする最もシンプルで効果的な方法は、毎日「ありがとう」と思えたことを3つ書き出すことです。
この行動は小さな時間ででき、継続するほど幸福感が高まりやすくなります。
米国カリフォルニア大学デービス校のロバート・エモンズ博士の研究によると、「感謝日記」をつけた人は、そうでない人に比べてポジティブな感情が増え、うつ症状が軽減されたと報告されています。
また、厚生労働省が紹介しているメンタルヘルスの指針でも、ポジティブな出来事に注目する習慣はストレス対処力を高めると示されています。
書き出す内容は特別な出来事である必要はありません。例えば以下のような小さな気づきで十分です。
・友人からLINEが届いた
・家族が夕食を作ってくれた
このように日常の中で見過ごしがちな「小さな幸せ」を言葉にすることで、脳がポジティブな記憶を優先的に探し出すようになります。
結果として、普段の生活そのものが「幸せを見つけやすい場」へと変化していくのです。
実例として、ある高校生が毎日寝る前に3つの感謝をノートに書く習慣を続けたところ、数週間で気分が安定し、クラスメイトとの関係も改善されたと話しています。
これは「感謝を書く」という行為が、思考の癖を不満から満足へと切り替えた好例です。
結論として、1日3つの感謝を書き出すことは、誰でも始められる簡単な行動でありながら、心を豊かに変える大きな効果をもたらします。
就寝前の「感謝リフレクション」習慣
1日の終わりに感謝を振り返る「感謝リフレクション」は、睡眠の質を高め、心を落ち着かせる効果があります。
人は寝る前に考えたことを記憶しやすいため、ポジティブな思考で一日を締めくくることは翌日の気分にも直結します。
国立精神・神経医療研究センターの資料でも、就寝前の思考内容は睡眠の深さや質に影響を与えると報告されています。
特に、感謝の気持ちは不安や緊張を和らげ、リラックス状態をつくる効果があるため、入眠をスムーズにしやすいのです。
実践の流れはとても簡単です。
1、ベッドに入ったら目を閉じる
2、今日一日で感謝できることを3つ思い出す
3、その出来事を思い浮かべながら「ありがとう」と心の中で唱える
例えば、「仕事を手伝ってくれた同僚に感謝」「温かい夕飯に感謝」「一日を無事に過ごせたことに感謝」など、些細なことで十分です。
ある企業でこの方法を社員に推奨したところ、睡眠不足に悩んでいた人が数週間で入眠が早くなり、翌日の集中力が高まったというケースもあります。
感謝が睡眠の質に影響することを示す実例です。
最終的に、この「感謝リフレクション」は感情を整える夜のルーティンとして定着させると大きな力を発揮します。
続けることで、安心した気持ちで眠りにつき、翌朝を心地よく迎えることができるのです。
感謝を深めるための実践テクニック
相手に直接伝える「感謝のフィードバック」
感謝の効果を強める方法のひとつが、心の中で思うだけでなく、相手に直接伝えることです。相手の行動に「ありがとう」と返すことで、双方の幸福感が高まり、関係性も深まります。
内閣府が実施した「国民生活に関する世論調査」では、家族や友人との人間関係に満足している人ほど生活全般の幸福度が高いという結果が出ています。
感謝を伝えることは、良好な人間関係を築くうえで欠かせない要素といえるでしょう。
また、米国心理学会(APA)の報告では、感謝の言葉を受け取った人は行動意欲が高まり、協力的になる傾向があると示されています。
具体的な実践例としては、職場で同僚に「助けてくれてありがとう」と声をかける、家族に「毎日ご飯を作ってくれてありがとう」と伝えるなどがあります。
小さなことでも言葉にすることで、相手は「自分が認められている」と感じ、信頼関係が強化されます。
実際に、ある学校で「感謝を伝える日」を設けたところ、生徒間のトラブルが減少し、学級全体の雰囲気が改善したという報告があります。
これは、言葉としてのフィードバックが、人間関係に大きな影響を与えることを示す好例です。
結局のところ、心で思うだけの感謝よりも、言葉で伝える感謝の方が効果は大きくなります。
感謝のフィードバックは、自分と相手の幸福度を同時に高める実践的な方法です。
小さな出来事に気づくマインドフルネス
感謝を深めるもう一つの方法は、日常の小さな出来事に意識を向ける「マインドフルネス」です。これは「今この瞬間に注意を向けること」であり、感謝の感度を高める鍵となります。
厚生労働省の「こころの耳」でも、マインドフルネスの活用はストレス対処や気分改善に効果があると紹介されています。
また、ハーバード大学の研究では、マインドフルネスを取り入れた人は幸福度が増し、うつ症状が軽減されたと報告されています。
小さな体験に気づくことが、感謝の習慣と直結することを裏付ける結果です。
実際の方法としては以下のようなステップが有効です。
・通勤中に聞こえる鳥の声に耳を傾ける
・夕食の味をしっかり感じながら食べる
このように日常の出来事に注意を向けることで「ありがたい」と感じられる場面が増えます。
ある主婦は、毎日夕食時に「今日の小さな幸せ」を家族でシェアする習慣を始めました。その結果、家庭内の会話が増え、家族のつながりが強まったと話しています。
小さな気づきが感謝に変わり、幸福感を広げた実例です。
最終的に、マインドフルネスは「感謝の感度を上げるレンズ」のような役割を果たします。日常にあふれる小さな出来事に気づくことで、感謝をより深く味わえるようになり、毎日の幸福感が自然と高まるのです。
感謝習慣と健康効果の科学的エビデンス
免疫力アップとの関連性
感謝を習慣にすると、体の免疫機能が高まることが研究によって示されています。
感謝を持つことでストレスが減少し、その結果、免疫システムが本来の力を発揮しやすくなるのです。
国立研究開発法人国立がん研究センターの「がん情報サービス」でも、慢性的なストレスが免疫力を下げ、病気のリスクを高めると説明されています。
逆に、前向きな感情や安心感を持つと、体の防御機能が安定することが確認されています。
米国カリフォルニア大学の研究では、感謝日記をつけている人は、そうでない人に比べて「炎症マーカー」が低く、心臓病や生活習慣病の予防につながる可能性があると報告されています。
免疫力を下げる炎症反応が抑えられる点は注目すべきポイントです。
実際に、ある病院のリハビリ患者を対象とした調査では、感謝の習慣を取り入れたグループの方が、風邪などの感染症にかかる頻度が少なかったと報告されています。
これは感謝が心理的な癒しだけでなく、身体面の防御力を高める具体的な効果を持つことを示す実例です。
結局のところ、感謝は単なる気持ちの問題ではなく、健康の土台を支える「免疫力のサポーター」としても働くのです。
習慣化すれば病気に強い体を育てることにつながります。
睡眠の質が改善される理由
感謝の習慣は、睡眠の質を高める効果も持っています。
人は寝る前に考えたことを記憶しやすいため、感謝の気持ちで一日を終えると、心が落ち着き眠りに入りやすくなるのです。
国立精神・神経医療研究センターの資料によれば、不安や緊張は睡眠の妨げになり、慢性的な不眠につながるとされています。
感謝を意識することは、こうした不安を和らげ、心身をリラックスさせる作用を持つのです。
米国マイアミ大学の研究では、感謝日記をつけている人の方が睡眠時間が長く、入眠までの時間も短いと報告されています。
ポジティブな思考が、体を安心させるホルモン分泌を促し、快眠につながっているのです。
例えば、ある会社員は「寝る前に3つの感謝を書き出す」ことを習慣にしました。
その結果、以前は寝つきが悪く夜中に目が覚めていたのが、数週間後には深く眠れるようになり、翌朝の目覚めも改善したと話しています。
結論として、感謝の習慣は「心を整えて眠りの質を上げる処方箋」となります。
睡眠の改善は翌日の集中力や気分にも直結するため、感謝は日常生活全体のパフォーマンスを底上げする効果を持っていると言えるでしょう。
感謝習慣を長続きさせるコツ
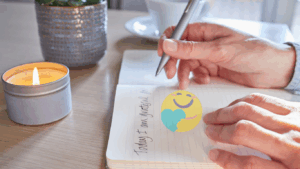
スマホや手帳を活用した仕組み化
感謝を習慣として続けるには「忘れない仕組み」を作ることが大切です。
人は忙しい日々の中で感謝の気持ちを意識することを後回しにしがちです。そのため、スマホや手帳を使って感謝を記録する環境を整えると、自然に継続できます。
厚生労働省が公開している「こころの健康づくり」でも、ポジティブな習慣は「日常生活の中で取り入れやすい形にすること」が成功のカギと示されています。
つまり、無理なく生活の一部に組み込む工夫が必要です。
具体的な方法の例を挙げます。
・専用アプリ(例:日記アプリ、習慣トラッカー)を利用して入力を続ける
・手帳やカレンダーの片隅に「ありがとう記録欄」を作る
実際に、ある会社員は通勤電車の中でスマホに感謝を書き留める習慣を始めました。
最初は「三日坊主になるかも」と思ったそうですが、アプリの通知が支えとなり、半年以上継続できています。今では日課となり、気持ちの安定に役立っていると話しています。
結局のところ、感謝を長く続ける秘訣は「思いついたときにすぐ書ける仕組み」を持つことです。スマホや手帳を活用することで習慣化がぐっと現実的になるでしょう。
家族や友人とシェアして相互作用を作る
感謝習慣を長続きさせるもう一つのコツは、周囲と共有することです。
自分だけでなく家族や友人と感謝を分かち合うことで、互いに刺激を受け合い、習慣を維持しやすくなります。
内閣府の「生活満足度調査」では、家族や友人との関係が充実している人ほど幸福度が高いと示されています。
感謝を共有することは、人間関係の質を高めると同時に、習慣を強化する効果を持つのです。
具体例としては次のような方法があります。
・友人同士で「感謝日記」を見せ合う
・LINEグループで「ありがとう投稿」を続ける
ある家庭では、寝る前に親子で「今日のありがとう」を伝え合う習慣を取り入れました。最初は子どもが照れて短い言葉しか出なかったそうですが、続けるうちに具体的な内容を話すようになり、家族の会話が増えたといいます。
これは、感謝の共有がコミュニケーションを自然に促す好例です。
まとめると、感謝は一人で抱えるよりも「誰かと分かち合う」ことで長く続けられます。家族や友人との相互作用が、習慣を支える強力なエネルギーとなるでしょう。
感謝を習慣にした人の変化事例
自己肯定感が高まり、挑戦意欲が向上
感謝の習慣は、自分を認める気持ちを育て、挑戦する力を後押しします。
日々の小さなことに感謝することで「自分には支えてくれる人や環境がある」と実感でき、それが自己肯定感の向上につながるのです。
文部科学省が発表した「子供の学び応援サイト」でも、自己肯定感が高い子どもは学習意欲や新しいことに挑戦する意欲が強いと紹介されています。
これは大人にも当てはまり、感謝の習慣が「自分ならできる」という前向きな気持ちを育てる効果を持つと考えられます。
実例として、ある大学生は就職活動中に「今日は支えてくれた人や良かった出来事を3つ書く」感謝日記を続けました。
その結果、以前より不安が減り、面接にも前向きな気持ちで挑めたと話しています。
自己肯定感が高まったことで、自信を持って行動できるようになったのです。
結局のところ、感謝を習慣にすることは「自分を信じる力」を育てます。
挑戦を避けるのではなく、一歩踏み出す勇気を自然に引き出す効果があるのです。
夫婦・親子関係の改善につながったケース
感謝を言葉や行動で伝える習慣は、家庭内の関係改善に直結します。
小さな「ありがとう」を積み重ねることで、相手への尊重や思いやりが可視化され、家族の絆が深まります。
内閣府の「家族・地域の絆に関する世論調査」では、家族に感謝や思いやりを伝えている人の方が生活満足度が高い傾向があると報告されています。
これは感謝が人間関係の質を高め、生活全体の幸福感を広げる根拠です。
実例を挙げると、ある夫婦は「寝る前に今日の感謝を一つ伝える」という習慣を取り入れました。
最初は気恥ずかしさもあったそうですが、続けるうちに会話が増え、以前よりも関係が良好になったといいます。
夫婦喧嘩が減り、協力し合う場面が増えたことも効果のひとつです。
また、ある家庭では親子で「ありがとう交換ノート」を始めました。
子どもが「ご飯を作ってくれてありがとう」と書き、親が「宿題を頑張ってくれてありがとう」と返す仕組みです。
続けるうちに親子の距離が縮まり、子どもの自己表現力も高まったと報告されています。
最終的に、感謝の習慣は夫婦や親子といった最も身近な関係性を穏やかに変えていきます。
小さな一言や行動が信頼を積み重ね、家庭全体の雰囲気を温かくする効果を生み出すのです。
感謝を続けた人のビフォーアフター比較
感謝の習慣は、始める前と続けた後でどのような違いを生むのでしょうか。ここでは実際の事例を「ビフォーアフター」で紹介します。
・ビフォー:
仕事のストレスが多く、上司や同僚への不満を抱えがち。毎朝気分が重く、週末になると疲労感で何もしたくなくなっていた。
・アフター:
毎晩「今日のありがとう」を3つ書き出す習慣を半年継続。職場で「小さな助け」に気づけるようになり、不満よりも感謝の方に意識が向くようになった。その結果、人間関係が円滑になり、プロジェクトでも積極的に協力できるようになった。
・ビフォー:
家事や育児が「当たり前」と思われている気がして、孤独感やイライラを感じることが多かった。子どもとの会話も減り、夫婦関係もぎくしゃくしていた。
・アフター:
家族で「ありがとう交換ノート」を始め、1日1回感謝を言葉にするようにした。1か月後には子どもが「洗濯してくれてありがとう」と自然に伝えるようになり、夫も「お弁当助かった」と言葉にするようになった。結果として、家庭内の雰囲気が大きく改善し、孤独感も和らいだ。
・ビフォー:
成績が伸びず、自信をなくしていた。友達と比較して落ち込むことが多く、挑戦する意欲も減少。
・アフター:
学校の課題で感謝日記をつけることになり、毎日友達や先生に対する「ありがとう」を書くようになった。2か月後には気持ちが安定し、以前よりも授業に集中できるようになった。自己肯定感が回復し、部活動でも積極的に行動できるようになった。
このように、感謝の習慣は単に気分を良くするだけでなく、行動や人間関係そのものを前向きに変化させます。
ビフォーの状態では「不満・孤独・不安」が中心だったのに対し、アフターでは「安心・信頼・挑戦」が増える傾向が明確に見られるのです。
結論として、感謝を継続することは「人生の質を根本から変える力」を持っています。わずかな習慣の違いが、大きな未来の差となって表れるのです。
感謝習慣のビフォーアフターまとめ
| 人物 | ビフォー(習慣前) | アフター(感謝習慣後) |
| 30代会社員 | ・職場の不満が多い ・朝から気分が重く週末は疲労感で動けない ・人間関係にストレス |
・毎晩「今日のありがとう」を3つ記録 ・小さな助けに気づきやすくなる ・協力的になりプロジェクトが円滑に進む |
| 40代主婦 | ・家事や育児が「当たり前」と思われ孤独感 ・子どもとの会話が減少 ・夫婦関係もぎくしゃく |
・家族で「ありがとう交換ノート」を実践 ・子どもや夫が自然に感謝を表現 ・家庭内の雰囲気が改善、孤独感が和らぐ |
| 高校生 | ・成績が伸びず自信を喪失 ・友達と比較して落ち込みがち ・挑戦意欲が低下 |
・毎日感謝日記を記入 ・気持ちが安定し集中力が回復 ・自己肯定感が高まり部活動にも積極的に参加 |
◆おすすめ《スポンサーリンク》
ココナラでお悩み相談・カウンセリング ![]()
まとめ
感謝を習慣化することは、幸福感を高めるだけでなく、心身や人間関係にも多くの効果をもたらします。
心理学的研究や実際の事例からも、その有効性は明らかであり、小さな「ありがとう」を積み重ねることが人生を豊かにする鍵となるのです。
今日から始められる習慣を続けて、自分自身の変化を体験してみて下さい。
1、感謝は幸福度を高める習慣
2、脳や体の健康をサポート
3、人間関係を円滑に改善
4、ビジネス成果にも直結する
5、続けるほど自己肯定感が向上
【関連記事「感謝の力が幸せを招く」】も合わせてご覧下さい。

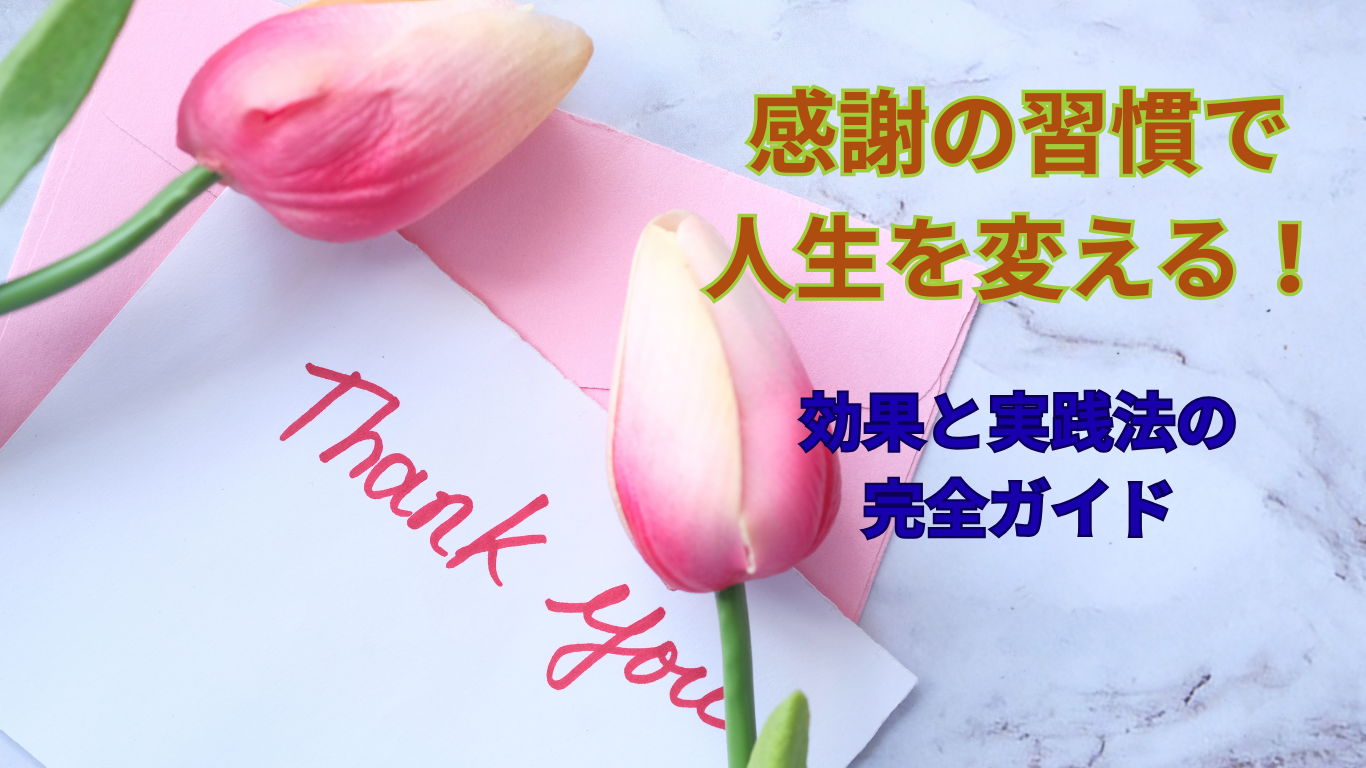



コメント