最近よく耳にする「ウェルビーイング」という言葉。気になって調べてみても、
「ウェルネス」や「ハピネス」との違いが分からなかったり、具体的にどんな方法で高めればよいのか悩んでいませんか?
この記事を読むことで、あなたは以下の内容が得られます。
① ウェルビーイングの本当の意味や定義が理解できる
② ウェルビーイングを高めるための具体的な方法・実践例がわかる
③ なぜ今ウェルビーイングが世界的に注目されているのか、その背景やメリットが明確
になる
本記事では世界保健機関(WHO)や国内外の専門家、企業の最新事例や口コミなど、信頼できる情報源をもとに分かりやすく解説します。
読み終えるころには、自分に合ったウェルビーイング向上の方法を理解し、今よりもずっと心身ともに充実した毎日を送れるようになっているでしょう。
ウェルビーイングの定義・基礎知識
ウェルビーイングとは何か?簡単な意味と由来
ウェルビーイング(well-being)という言葉を最近よく耳にしますね。でも、その意味をはっきり説明できる人は意外と少ないかもしれません。
簡単に言えば、ウェルビーイングとは「心も体も健康で、毎日の生活が充実していて幸せな状態」のことを言います。
この言葉が初めて登場したのは1946年、世界保健機関(WHO)が健康を定義した時でした。WHOは、健康を「ただ病気がないだけでなく、体も心も社会的にも満たされた状態」だと考えました。
つまり、体が元気なだけではなく、心も穏やかで、人間関係も良好であることが本当の健康であると世界が認めたのです。
ウェルビーイングは、単に「幸せ」という意味のハピネス(happiness)よりも広い概念です。ハピネスは一時的な喜びを意味しますが、ウェルビーイングはもっと深くて長続きする幸せや満足感を含みます。
また、体の健康を中心に考えるウェルネス(wellness)と比べても、ウェルビーイングは体だけでなく、心や社会生活まで含めた総合的な健康を指しています。
ハピネス・ウェルネスとの違いとは?
ウェルビーイングの理解を深めるために、似ている言葉「ハピネス」と「ウェルネス」との違いを整理してみましょう。
<ポイント整理>
短期間の幸せや一時的な喜びを感じること。
例えば、美味しいものを食べたり好きなことをしている時に感じる幸せです。
・ウェルネス(wellness):
体の健康を中心に、規則正しい生活やバランスの良い食事、運動などで体調を整えること。体が健康であることを重視します。
・ウェルビーイング(well-being):
体だけでなく心や社会的な人間関係、生活環境まで含めて、自分自身が満たされている状態を指します。
短期間だけでなく、長期的に持続する心地よさを大切にします。
実際の例で考えてみましょう。
例えば、毎日運動をして健康的な食事を取っている人はウェルネスが高いです。
一方、友達や家族との関係が良く、仕事や学校でもやりがいを感じている人はウェルビーイングが高いといえます。
ウェルビーイングは人生全体の幸福度を測る概念であり、広い視野で幸せを考えることが特徴です。
今ウェルビーイングが注目される社会的背景
なぜ今、ウェルビーイングがこんなに注目されているのでしょうか?そこには現代社会が抱えるいくつかの大きな理由があります。
まず一つ目の理由は、ストレス社会です。
厚生労働省の調査(令和2年)によると、日本の成人の約6割以上が日常的にストレスを感じていると答えています。学校や仕事での競争、SNSでの人間関係など、心の負担が増えたことがウェルビーイングの重要性を高めています。
二つ目の理由は、人生に求めるものが変化していることです。
昔は経済的な豊かさや物質的な満足感が幸福だと考えられていましたが、近年の研究(世界幸福度調査2023)では、人間関係や精神的な満足感の方が、幸福度に強い影響を与えることがわかってきました。物やお金だけでは本当の幸せを感じにくくなり、心や社会的つながりを重視するようになっています。
また、近年ではSDGs(持続可能な開発目標)の取り組みも注目されていますね。その中の一つに「すべての人に健康と福祉を(Good Health and Well-being)」という項目があり、国や企業も積極的にウェルビーイング向上のために動き出しています。
大手企業では、従業員のウェルビーイングを高めるための取り組み(柔軟な働き方やリラックスできる職場環境の整備)が行われ始めました。
例えば、Googleでは従業員のためにリラクゼーションスペースやマインドフルネスの時間を取り入れており、働く人が幸せを感じながら仕事ができる環境を作っています。
日本でも、パナソニックやトヨタ自動車がウェルビーイング経営を取り入れており、
働く人の幸福度を高めようとしています。
このように、社会が変化し、人々が求める「幸せ」の内容も変わってきたことで、ウェルビーイングは今、大きな注目を浴びているのです。
最後に改めて整理すると、ウェルビーイングとは、
「体だけでなく、心も人間関係も満たされている幸せな状態」です。
私たちが生きていく上でとても大切な考え方であり、世界的にもますます注目されることでしょう。
これからの人生をより幸せで充実したものにするために、ウェルビーイングの考え方を取り入れてみてはいかがでしょうか?
ウェルビーイングが成り立つ条件
ウェルビーイングとは、体や心、人間関係、生活環境などが満たされている状態のことを言います。
実は、ウェルビーイングが成り立つためには、いくつかの大切な条件があります。
その中でも特に重要なのは次の3つです。
1、心身の健康(身体的・精神的ウェルビーイング)
まず第一に、心と体が健康であることが欠かせません。
体が元気でも心が疲れていると幸せを感じにくいですし、心が元気でも体調が悪いと満足な生活は難しくなります。
ウェルビーイングでは、心と体の両方が整っていることがポイントです。
世界保健機関(WHO)は、健康を「病気や障害がないことだけでなく、体も心も社会的にも完全に良い状態であること」と定義しています。つまり、心と体の両方のバランスが大切なのです。
例えば、体の健康を維持するためには、毎日の食事や睡眠、適度な運動が必要です。
また、心の健康には、自分を大切にする時間を持ったり、ストレスをうまく解消したりすることが有効になります。
私の知り合いに、中学校の頃から運動が苦手で、気持ちが沈みがちだった人がいます。その人は大人になってから、ウォーキングを始めました。すると、少しずつ体調が良くなっただけでなく、気持ちも前向きになったと言います。
心と体は密接に関わっているため、どちらか一方を整えるだけでも良い影響が出やすいのですね。
2、良好な人間関係(社会的ウェルビーイング)
二つ目の条件は、良好な人間関係があることです。
人は一人では生きていけません。家族や友達、職場や学校の人間関係が良好だと、安心して過ごせます。
反対に、人間関係が悪化するとストレスを感じ、幸せを感じにくくなるでしょう。
OECD(経済協力開発機構)が行った調査によると、人生の満足度が高い人は良好な人間関係を築いている傾向があります。また、人間関係が良い人ほどストレスを感じにくく、心身の健康を維持しやすいという結果も出ています。
私自身も、学生時代に友達とうまくいかなかった時期がありました。その時は毎日学校に行くのが辛くて仕方ありませんでした。しかし、部活で自分の趣味を共有できる仲間を見つけたことで、少しずつ気持ちが楽になりました。
良い人間関係は、心を支える大切な要素なのです。
3、安定した生活基盤(経済的ウェルビーイング)
三つ目は、安定した生活環境、特に経済的な安定です。
生活をするためには、最低限のお金や住む場所、衣食住が安定している必要があります。お金がすべてではありませんが、経済的に不安定な状態が続くと、心も落ち着かず、ストレスが溜まりやすくなります。
実際、内閣府の調査によると、経済的に安定している人のほうが、人生への満足度が高い傾向があります。また、経済的な不安は心身の健康にも影響を与えやすく、長期間続くと精神的に疲れてしまうことが明らかになっています。
私がボランティアで関わったある家庭では、親が失業して経済的に苦しい時期がありました。その間、家族全員が不安で落ち着かない日々を過ごしていました。しかし、その後親が再就職し経済的に安定すると、家族全員の表情が明るくなり、家族仲も以前より良くなったのです。
生活が安定することは、家族の幸せにも直結する重要な要素だと実感しました。
3つの条件のまとめ
ウェルビーイングが成り立つための重要な3つの条件をもう一度おさらいします。
・良好な人間関係が築けていること(社会的ウェルビーイング)
・安定した生活基盤があること(経済的ウェルビーイング)
これらの条件はそれぞれが単独で成り立つものではなく、お互いに深く関連しています。一つの条件を整えることで、他の条件にも良い影響が波及しやすくなります。
ウェルビーイングを高めたいと感じている方は、まずは自分が最も取り組みやすい分野から改善していくことがおすすめです。
小さなことから始めて、心身ともに満たされた毎日を目指しましょう。
ウェルビーイングの実例・口コミや評判
ウェルビーイングの意味が分かっても、実際にどのように取り入れればよいのか、
イメージしにくい人も多いかもしれません。
ここでは、企業の取り組みや個人の口コミ、SNSなどでの評判を紹介しながら、具体的なイメージを持てるように説明していきましょう。
企業の取り組み・成功事例
最近、多くの企業がウェルビーイング向上のためにさまざまな工夫をしています。
なぜなら、働く人たちが幸せだと会社も元気になることが分かったからです。
実際、経済産業省の調査でも、ウェルビーイングを大切にする企業ほど、社員の生産性が高まり、会社全体の業績も良くなるという結果が出ています。
【企業のウェルビーイングへの取り組み例】
社員がリラックスできるスペースを社内に作ったり、マインドフルネス瞑想を取り入れたりしています。仕事のストレスを減らして、社員が自由にアイデアを出せるようにサポートしています。
在宅勤務を増やしたり、勤務時間を柔軟に調整したりして、仕事とプライベートのバランスを取りやすくしています。その結果、社員が家庭や趣味の時間を増やすことができ、人生の満足度が高まりました。
このように、働く人たちのウェルビーイングを高めるために、さまざまな取り組みをしている企業は増えています。
働く人が幸せになれば、会社にもプラスの影響があるということですね。
個人の口コミ・体験談
次に、実際にウェルビーイングを意識して生活を変えた人の体験談を紹介します。
これは私の知人であるミサさん(仮名)の話です。
ミサさんは、仕事が忙しくストレスをため込み、よく体調を崩していました。
そんな彼女はある日、「ウェルビーイング」という考え方を知り、自分の生活を少し変えてみようと思いました。
彼女が取り組んだことは次の3つです。
・毎日寝る前に5分間、深呼吸をする(心の健康を整える)。
・週末に友達や家族とゆっくり過ごす時間を作る(人間関係を良くする)。
・無理して仕事をせず、疲れたら休憩を取る(身体の健康を整える)。
これらを始めてから、ミサさんはストレスが減り、心も体も調子が良くなったと話しています。
彼女のように、小さなことからでもウェルビーイングを意識して取り組むことで、人生が変わることがあるのです。
SNSでの評判や実際の声
最近では、SNS上でもウェルビーイングが話題になっています。TwitterやInstagramなどでも、自分らしく健康的な生活を楽しむ人たちが増えているのを見かけます。
例えば、SNSでよく見られるウェルビーイングに関する投稿は次のようなものです。
「朝ヨガを続けていたら、ストレスが減って気持ちが落ち着くようになった。」
「スマホを使う時間を減らして、本を読む時間を増やしたら、心がスッキリして眠りも良くなった。」
「お金をたくさん稼ぐより、自分が本当に好きなことをする方が毎日幸せだと気付いた。」
こうした投稿からも、ウェルビーイングは難しいことではなく、ちょっとした工夫で誰でも始められるものだと分かりますね。
ウェルビーイングを実践するポイント
ここまでの企業の取り組みや個人の体験談、SNSの声を参考にして、ウェルビーイングを実践するためのポイントをまとめてみます。
・心と体、そして人とのつながりをバランス良く大切にする。
・小さなことから始めて習慣化する。
ウェルビーイングを高めるためには特別なことをしなくても、少しずつ自分の生活を良くしていけばいいのです。皆さんもぜひ、自分に合った方法で毎日をより幸せにしてみてくださいね。
ウェルビーイングを高める方法とコツ
日常生活で実践できる具体的方法
ウェルビーイングは、自分の心と体を健康で幸せな状態に整えることです。
毎日の生活の中で、特別なことをしなくても簡単に実践できる方法があります。
大切なのは、小さな工夫を続けることですよ。
実際に取り組みやすい方法を3つ紹介します。
・寝る前のスマホ利用を減らす
スマホやパソコンの画面を寝る直前まで見ていると、脳が休まりにくくなり、睡眠の質が落ちてしまいます。世界保健機関(WHO)も、睡眠不足が心身の健康に悪影響を及ぼすと指摘していました。
寝る1時間前には画面を見るのをやめて、本を読んだり音楽を聞いたりすると、ぐっすり眠れて翌朝スッキリ起きられます。
・簡単な運動を毎日少しずつ行う
厚生労働省は、1日に15~30分の軽い運動が健康維持に役立つと言っています。激しい運動じゃなくても、ウォーキングやストレッチをするだけで十分効果的です。運動を続けると、気持ちが前向きになったり、ストレスが軽くなったりします。
・感謝の気持ちを書き出す
ノートやスマホに、毎日寝る前に「今日感謝したこと」を3つ書いてみましょう。例えば、「友達が宿題を教えてくれた」「夕飯が美味しかった」など、小さなことで構いません。感謝の気持ちを書く習慣がつくと、心が穏やかになって、幸福感が増しますよ。
自分に合った方法の選び方とポイント
ウェルビーイングを高めるためには、自分が「心地よい」「楽しい」と感じる方法を見つけることが重要です。友達にとって良い方法が、自分に合うとは限りません。
まずは、自分がどんなことを好きで、何をしたら気分が良くなるのかを考えてみましょう。
・自分の好きなことや得意なことを書き出してみる。
・無理なく毎日続けられそうなことを探す。
・少しでも試してみて、自分が楽しめるかをチェックする。
私自身も最初は「運動が良い」と聞いてジョギングを始めましたが、走るのが苦手だったため、逆にストレスになりました。その後、ヨガを試してみたらリラックスできて心地良さを感じることができました。
人それぞれ性格や好みが違うので、自分にぴったりの方法を見つけることが何よりも大切なことなのです。
継続するためのコツと習慣化のヒント
ウェルビーイングを高めるためには、続けることが一番大事。でも、「毎日続ける」って簡単そうでなかなか難しいですよね。そこで、続けやすくするためのヒントをお伝えします。
・小さなことから始める
初めから「毎日30分ジョギングする!」と決めるのではなく、「まずは5分だけ歩いてみよう」など、簡単な目標からスタートしましょう。達成感が得やすくなり、続けることが楽しくなりますよ。
・決まった時間や場所で行う
例えば「朝起きたらベッドの横でストレッチをする」と決めるなど、毎日同じタイミングや場所で行うようにすると、体が自然とその行動を覚えて続けやすくなります。
・「やらなきゃ」より「やりたい」と思えるように工夫する
義務的になると楽しくありません。自分へのご褒美を用意したり、好きな音楽を聴きながらやったりすると楽しみになり、継続が苦にならなくなりますよ。
私の友人は、「3日坊主でも気にしない」をモットーにしています。続けられなくて落ち込むよりも、「また明日からやればいい!」と気軽に考えることで、かえって長く続けられるようになったそうです。
完璧を目指さず、ゆったりと続けるのがポイントですね。
ウェルビーイングは、特別なことをしなくても、毎日のちょっとした工夫で誰でも高められます。自分が楽しめる方法を見つけて、ぜひ気楽に始めてみてください。
ウェルビーイング向上で注意したいリスクと対処法
ウェルビーイングを高めることは、毎日の生活をより幸せにするために役立ちます。
ただ、ウェルビーイングに取り組む時にも気をつけるべきことがあります。ここでは、特に気をつけたい3つのポイントと、その対処法をわかりやすくお伝えしますね。
完璧主義がストレスになるリスク
ウェルビーイングを目指す人の中には、「完璧主義」になってしまう人もいます。
例えば、「毎日運動を必ず30分やらなければいけない」とか、「食事は絶対に健康的でなければいけない」と自分に厳しくなりすぎると、かえってストレスが溜まってしまうことがあります。
厚生労働省の調査でも、「健康や幸せを追求しすぎて逆にストレスを感じてしまった」という人が一定数いることが報告されています。
せっかくのウェルビーイングへの取り組みが、無理をしすぎることでかえって逆効果になってしまうことがあるのです。
・目標は緩めに設定する。「毎日必ず」ではなく、「週に何回か」と考える。
・達成できなくても自分を責めない。
「今日は無理だったけど、また明日やろう」と気軽に考える。
実際に、私の知人にも「完璧にやろうとして挫折した」という人がいましたが、目標を緩めて楽しむようにしたところ、長続きするようになりました。
自分に合わない方法による逆効果への注意
ウェルビーイングを高める方法はたくさんあります。でも、誰にでも合う万能な方法というものはありません。友達が成功した方法が、自分には合わないことだってよくあります。
例えば、「早起きがいい」と聞いて早起きを頑張ったけれど、朝が苦手で続かずストレスになってしまった、という話もよく聞きます。
世界保健機関(WHO)でも、「人には個人差があり、自分に合った方法で取り組むことが大切」と伝えています。
・他人がやっているからといって、無理に真似しない。
・色々な方法を少しずつ試してみて、自分に合うものを見つける。
・合わないと感じたらすぐにやめて別の方法を試す。
私自身も「ジョギングが健康にいい」と聞いて挑戦しましたが、走るのが苦手だったため、毎回ストレスになりました。
そこで、自分に合っているウォーキングに切り替えたら、毎日続けられるようになって体の調子も良くなりました。
ウェルビーイング疲れを避けるための対策
ウェルビーイングを高めようと頑張りすぎると、逆に「ウェルビーイング疲れ」になってしまうことがあります。
健康のために毎日頑張っていることが、いつの間にか義務になり、気持ちが疲れてしまう状態です。
内閣府の調査によると、「健康のための努力が、かえって精神的な疲労を招くことがある」と指摘されています。
これは、無理に習慣化しようとするとプレッシャーがかかり、気持ちがついていかなくなるためです。
・疲れを感じたら、すぐに一旦休む。
・ウェルビーイング向上のための行動は「楽しむこと」を目的にする。
・時には何もしない日を作って、自由に過ごす。
私の友達も「毎日運動しなきゃ!」と思っていましたが、プレッシャーを感じてしまい逆効果でした。そこで「今日は疲れているから休もう」と素直に休息を取ったところ、次の日からまた楽しく運動が続けられるようになったそうです。
3つのリスクを避けるためのポイントまとめ
ウェルビーイングを高めるときには、次のポイントを意識すると上手くいきます。
・他人に合った方法ではなく、自分に合った方法を選ぶ。
・ウェルビーイング疲れにならないように、疲れを感じたら休息する。
ウェルビーイングは、自分が心地よく、楽しく続けられることが一番大切です。
頑張りすぎず、自分らしいペースでゆるやかに楽しみながら取り組んでみてください。
ウェルビーイング向上のための実践手順

ウェルビーイングを高めて毎日をもっと幸せにしたいと思ったら、まずは自分が今どんな状態なのかを知ることが大切です。
そして、目標を決めて具体的に行動していきましょう。ここからは、ウェルビーイングを高めるためのわかりやすい手順を順番にお伝えします。
現状のウェルビーイングを把握する方法
まず最初に、自分の現在の状態をチェックしましょう。
ウェルビーイングとは、身体・心・人間関係・生活環境など、さまざまな要素が関わっています。今の自分の状態を知ることで、改善したいポイントが見つかりますよ。
チェックする項目をまとめましたので、以下の質問に答えてみてください。
・最近ぐっすり眠れていますか?
・体調は良好ですか?(風邪をひきやすい、疲れやすいなど)
・気分が落ち込むことはありませんか?
・学校や職場の人間関係は良好ですか?
・家庭や友達との関係はうまくいっていますか?
・好きなことや趣味を楽しむ時間を持てていますか?
この質問に答えると、自分がどの部分に問題を抱えているか分かります。
例えば「最近眠れていない」と感じるなら、睡眠環境を改善することが必要ですね。
厚生労働省の調査でも、睡眠不足は心と身体の両方に悪影響を与えることが分かっています。だからこそ、自分の状態を知ることはウェルビーイングを高める第一歩になるのです。
具体的な目標設定とアクションプランの立て方
自分の状態が分かったら、次は改善したい部分に目標を設定しましょう。
目標はあまり大きくなく、小さく具体的に決めるのがコツです。
例えば、「毎日30分運動をする」と決めると続けるのが難しいこともあります。そこで、最初は「毎日5分ストレッチをする」と小さな目標を立ててみましょう。その方が気軽に取り組めて続けやすいですよ。
・睡眠不足の人:「寝る30分前にスマホを見ない」
・運動不足の人:「毎朝5分だけ散歩する」
・ストレスが多い人:「寝る前に1日の良かったことを3つ書く」
私の知り合いは、仕事のストレスが多くて悩んでいました。そこで、寝る前に3つの良かったことを書き出すことにしたそうです。
最初は小さなことからでしたが、「お昼ご飯が美味しかった」「友達と話せてよかった」など、小さな幸せを見つける習慣がついたと言います。こうして少しずつ心が軽くなり、ストレスも減ったそうです。
継続のための振り返りと改善方法
ウェルビーイング向上のためには、続けることが重要です。
でも、ずっと同じことを続けるのは難しい時もあります。そこで、定期的に自分のやっていることを振り返り、無理なく続けられるように工夫しましょう。
以下の方法で振り返りを行ってみてください。
・1週間に1回、自分が決めたことができたか振り返る。
・無理があった場合は、目標をさらに小さく調整する。
・続いていることがあれば、自分を褒めてあげる。
例えば、「毎朝5分の散歩」を決めていたけれど、実際には毎日は難しかったと感じるなら、「週に3回、気分が良い時だけ散歩をする」に変更しても大丈夫です。
大切なのは「続けること」なので、自分が気楽に続けられるように調整しましょう。
私も最初は「毎日20分ヨガをする」と決めましたが、疲れた日はできずに挫折しそうになりました。そこで「週に3回、できる時に10分だけやる」に変更すると、無理なく続けられるようになりました。
ウェルビーイングを高めるためには、自分を責めずに、小さなことを楽しみながらコツコツと続けることがポイントです。
自分なりのペースで、少しずつウェルビーイングを向上させていきましょう。
ウェルビーイング向上に役立つおすすめ商品・サービス
ウェルビーイングを向上させるには、自分の力だけでなく、便利な商品やサービスを活用することも有効です。
特に最近は、スマートフォンのアプリや便利なグッズなど、手軽にウェルビーイングを高められるアイテムがたくさん登場しています。
今回は、日常生活で気軽に利用できるものを、実際の利用者の声と共に紹介しましょう。
心と体を整えるアプリやサービス
まず最初に紹介するのは、心や体の健康をサポートしてくれる便利なスマートフォンアプリです。
最近では、「瞑想(めいそう)」や「マインドフルネス」と呼ばれる、心を穏やかに整える方法が注目されています。厚生労働省によると、マインドフルネスを日常生活に取り入れることで、ストレスが軽減され心の健康に役立つと報告されています。
・Meditopia(メディトピア)
短い時間でできる簡単な瞑想を教えてくれるアプリです。中学生や高校生でも簡単に使える内容で、毎日の気分が落ち着くと好評です。
・FiNC(フィンク)
毎日の運動や食事の記録を取ったり、簡単な運動メニューを教えてくれるアプリです。運動が苦手な人でも気軽に使える工夫がされています。
実際、私の友人もMeditopiaを使って、「寝る前に数分の瞑想をするだけで、ぐっすり眠れるようになった」と言っています。スマホがあれば簡単に始められるので、ぜひ試してみてくださいね。
リラクゼーションや睡眠改善におすすめのアイテム
次に、リラックスしたり、良質な睡眠を取るために役立つアイテムを紹介します。
国立精神・神経医療研究センターの調査によると、日本人の約3割が睡眠に問題を抱えているそうです。十分な睡眠をとることは、ウェルビーイングを高めるためにとても重要なのです。
・アロマディフューザー
リラックス効果のある香りを部屋に広げてくれる機械です。ラベンダーやオレンジなど好きな香りを選んで楽しめます。
・快眠枕(かいみんまくら)
頭や首の形に合わせて優しくフィットし、気持ちよく眠れるように工夫された枕です。睡眠の質が良くなり、目覚めがスッキリします。
私自身、アロマディフューザーを寝る前に使うようになってから、眠りが深くなり、毎朝気持ちよく起きられるようになりました。寝つきが悪いと感じている人は、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。
専門家と繋がれるオンライン相談サービス
最後に紹介するのは、専門家に気軽に相談できるオンラインサービスです。
心や体の悩みを一人で抱え込まずに、プロのアドバイスを聞くことはとても大切です。最近ではオンラインで簡単に相談ができるようになりました。
・cotree(コトリー)
心理カウンセラーとオンラインで相談ができるサービスです。メールやチャットで気軽に相談できるため、誰にも知られずに悩みを打ち明けることができます。
・Doctors Me(ドクターズミー)
医師や看護師、カウンセラーなど、さまざまな専門家にオンラインで相談できるサービスです。心配なことがあれば、いつでもプロの意見を聞くことができます。
実際、学校の友達関係で悩んでいた知人は、cotreeを利用して悩みを相談したそうです。相談したことで、気持ちがスッキリして前向きになれたと言っていました。専門家とつながることは、自分では気づけなかった解決策が見つかるきっかけにもなります。
おすすめ商品・サービスの活用ポイント
最後に、これらの商品やサービスをうまく活用するポイントをまとめておきましょう。
・無理なく取り入れられるものから始める
・自分に合っているか試しながら利用する
・効果を感じたものを継続して使う
ウェルビーイングを高めるには、便利なアイテムやサービスを使って気軽に楽しみながら行うのが一番です。自分に合った方法を見つけて、ぜひ毎日の生活をより豊かなものにしてくださいね。
◆おすすめ《スポンサーリンク》アロマテラピーのある暮らしを【フレーバーライフ】 ![]()
まとめ
ウェルビーイングとは、心身や人間関係など人生全体が満たされた状態を指します。
この記事では、ウェルビーイングの意味や高め方、実践例を紹介しました。
ポイントを振り返ると、
1、心身健康が基盤
2、良好な人間関係
3、生活基盤の安定
4、自分に合う方法選択
5、無理なく習慣化する
以上を意識しながら、自分のペースで毎日の生活に取り入れてみて下さい。
【参考記事】「ストレスに悩むビジネスパーソン必見!初心者でもできる瞑想・マインドフルネスの効果とやり方」も参考にしてみてくださいね。

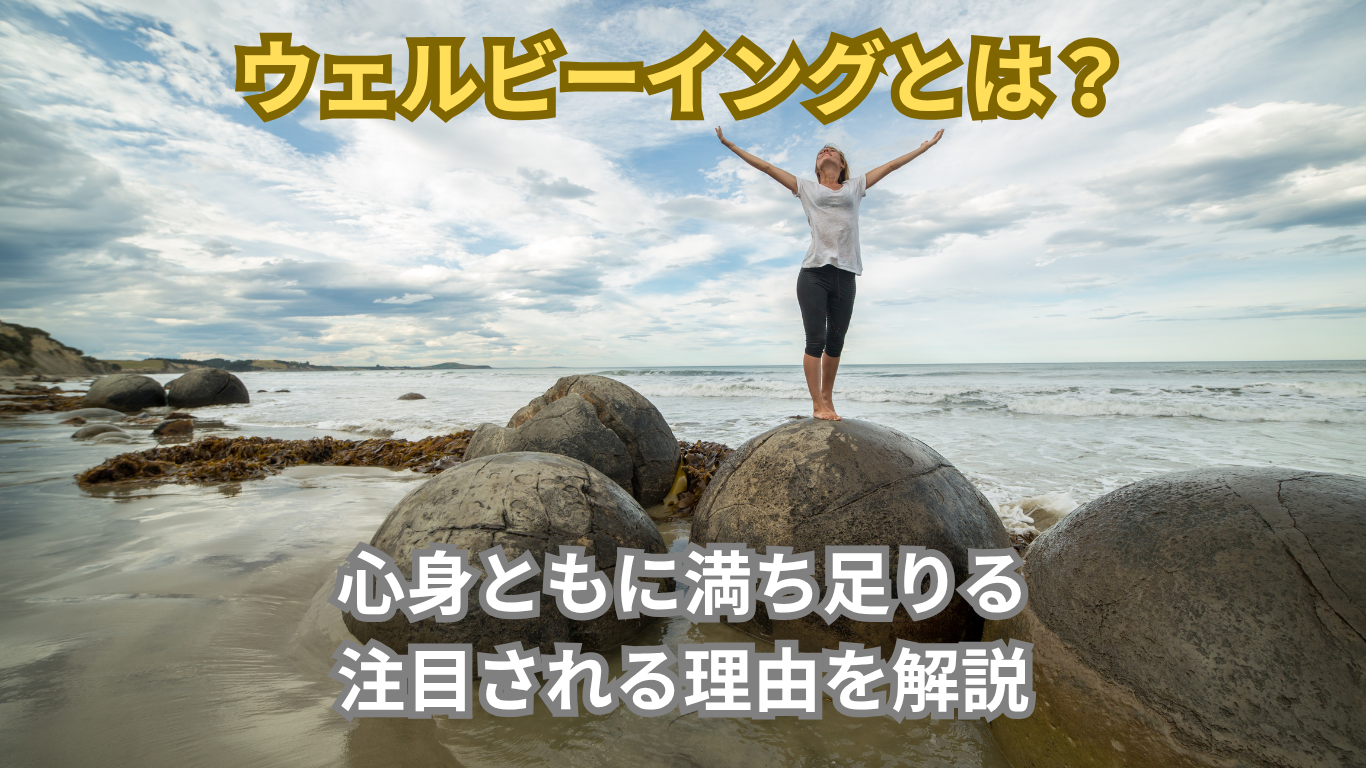



コメント